
10/23(木)、コンペティション『ロス・ホンゴス』の上映後に、オスカル・ルイス・ナビア監督とプロデューサーのゲルリー・ポランコさんのQ&Aが行われました。
⇒作品詳細
Q:監督の故郷で撮られた映画ということですが、どうして故郷に帰って映画を撮ろうと思われたのですか。そのいきさつから教えてくださいますか。
オスカル・ルイス・ナビア監督(以下、監督):まず、この映画を撮ったきっかけですけれども、私はヒトエ(別の場所?)に住んでいましたが、祖母が急に癌になったという知らせをうけ、故郷に戻りました。祖母が急に亡くなったことは、私にとってとても大きな人生の転機となりました。そこで私自身、LIFE(=命、生きること、人生)を深く考えるようになりまして、ぜひ、その「LIFE」についての映画を撮りたいと思いました。「命」というテーマはとても重要なことだと思い、そこからいろいろ私自身の思い出を思い出して映画をつくったのです。
そして、二人のまったく異なる主人公の友情物語を描きたいと思ったわけです。この二人の主人公というのは、まったく違ったバックグラウンドを持っていて、社会的階層も生まれ育った地区も違います。唯一、彼らが共有していることが、絵を書くことに対する憧れや好きだという気持ちです。彼らは生命にみなぎっていて、若いからこそ、反逆心があったり、これからの人生に対する希望があったりします。そういったところを描きたいと思いました。
Q:料理のシーンが印象的でした。何か、こだわって撮影されたことはあるのでしょうか。卵とかサラダとかとてもおいしそうでした。
監督:料理についての質問を受けたのは初めてです。私自身とてもサイメリアンの映画が大好きなのですが、それに感化されて映画の中に料理を入れてみようかなと思いました。私自身が映画監督ですが、映画を見ることが大好きですし、映画から影響を受けています。
卵は、私にとって日常的にあります。卵とトマトを一緒にした料理が出てきますが、これは実は私の祖母がよく作っていました。もう一つ、卵だけの料理がRASの家で登場しますが、これもよく夕飯のおかずとして出てきます。卵というのは母親・オリジン(原点)と思っていますので、私は卵料理もいれたわけです。
映画の中で食べているシーンを撮影するということは、対象物、つまり主人公や状況を象徴するものだと思います。何を食べているか、どうやって食べているかということが、その人物を象徴するのだと思います。すごく深い意味があるのだと思います。
Q:監督はニーニーたちのことをどれだけ心配しているのでしょうか。彼らについてどのように思っているのでしょうか。
監督:私が思うに、現実というのはいろんなレベルであると思います。お婆さんをとりまく現実があり、お母さんをとりまく現実、お父さんをとりまく現実があります。こういった現実は小宇宙と言っていいでしょう。これらが共存して私たちの現実があり、それが人生であると私は思っています。
考えてみると、いま私たちはこの瞬間にこの劇場にいますが、同じ瞬間にどこか別の国では誰かが道端で殺されているかもしれない。この劇場にいるという現実において、(観客を指して)あなたは明日のことを考えているかもしれない。(別の観客を指して)あなたは今晩何を食べようか考えているかもしれない。私たちが共有していることと、頭の中で考えていること全部が共存していることが現実だと思います。
それをあえて私は映画の中で描きたいと思いました。この現実は、もしかしたら夢・過去・将来・未来もふくまれているかもしれない。そういったものが全部ミックスされているかもしれない。それを描きたいと思ったのです。
とくにラストシーンは、もしかしたら、現実ではないかもしれません。ただの夢かもしれないし、これから起きることかもしれないし、すでに起こったことかもしれません。そういったことで描いているわけです。
それから、政治の描写についてですが、私は政治を非常に真剣に考えています。だからといって、私の政治に対する意見を、映画を通してはっきりと、こうだ、こうあるべきだ、というような説教がましい描き方をしたいとも思っていません。それは、やはりみなさんが考えて共感していただきたい、共感しなくても考えていただきたいと思うからです。
もうひとついえることは、あらゆるすべての映画が政治的であると私は考えています。『バットマン』も『スパイダーマン』もある意味政治的です。決して、政治を語ることをスキップしたくないと私は思います。
私の国が抱えている政治的状況は大変難しい状況だと思います。だからといって、私は不平不満を言いたいと思っているわけではありません。そうではなくて、私は人生・生きることを賛歌したいと思っています。若い人たち、年齢という意味だけではなく、考え方が若いとか、自分が何か国を変えたいという強い思いをもっている人たちも若いと括っていいと思います。そういう人たちを描きたいと思っていました。
Q:ラストの木のシーンがとても印象的でした。登場人物は全員プロの俳優ではないと思いましたが、その中でRASとカルヴィンは、本当にストリートアーティストとして生計を立てていているのでしょうか。監督と俳優との出会いの経緯を教えてください。
監督:あの木はサマンという木で樹齢250年です。2ヶ月ほど探していて、幸運にも見つけました。最後のシーンは全くエフェクトを使っておらず、自然に白いコケが垂れ下がっています。古い木なので、コケが生えているんです。自然光で魔法のような光を待って撮影しました。本当に古い手法で撮りました。
俳優陣ですが、プロの俳優は一人もいません。実際の自分と近い人物を演じてもらっています。RASもカルヴィンも現実の彼らの名前です。お父さん役は私の本当のお父さんです。お婆さん役は、私のお婆さんの姉妹です。絵を描いている若い子たちは、実際に描いています。年齢の高い画家たちも、実際に壁に絵を書いているグラフィティアーティストたちです。
主人公たちを探すために、私は1年半かけて高校生など900人ほどにインタビューしました。いろんな話を聞いて、グラフィティアーティストたちにもたくさん調査しました。カリのマリオワイズという25年間壁画を描いている人にもインタビューして、映画にも出演していただきたいとお願いしました。
私はそもそも脚本を書いています。フィクションを考えて脚本を書くわけですが、同時進行で、現実にいる人たちに話を聞いて、それを自分の作品の中に織り込むということが大好きなのです。ですから、常に脚本は改稿していきますし、始まったあとも、撮影しながら脚本を変えていくことが多々あります。それと、共同脚本家たちと話をして、彼らから台詞のアイディアをもらって書いていきますが、そういう作り方のほうが、より本物感を出すことができ、ユニークなものがつくれると思っています。
簡単に言ってしまいますと、RASはRASなんです。RASが他の登場人物を演じようとしていなくて、RASはRAS自身としてこの映画に出ている。そういったことがこの映画はユニークでいいと私は思っています。
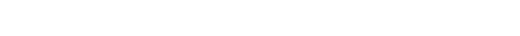


















 Check
Check





