
10/26(日)、 日本映画スプラッシュ『Starting Over』の上映後、西原孝至監督Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
Q:今、改めてスクリーンで作品をご覧になった感想をお願いいたします。
西原孝至監督(以下、監督):本当にホッとしたというのが一番の感想です。この作品は一番最初に脚本を書いたのが25歳くらいのときで、それから知り合ったプロデューサの方に読んでもらって「撮りたいんですけど」という話をしたのですが、なかなか無名の新人監督にはチャンスが巡ってきませんでした。この作品の前に映画は撮らせてもらったのですが、この作品は自分の納得のいく形で撮りたいなと思っていて、コツコツ貯金をしてやっと去年メドが立ちました。知り合いのスタッフとかキャストさんにもお金がなかったということもあって色々迷惑をかけちゃったんですけど、ようやく去年の11月くらいから半年くらい撮影して、さらに半年くらい編集して、そしたらちょうどこの東京国際映画祭に呼んでいただけることになりました。本当に僕は映画祭にエントリーしたいなと思っていたんですけど、まさかこんなに早く決まるとは思っていなくて、前の作品は公開するまでに2年かかりましたので、今回のことは本当にびっくりしています。
Q:本当に完成おめでとうございます。今、25歳のときから脚本を書き始めたとおっしゃっていましたが、最初からこの2人の女性の物語を書こうと思われていたのか、もしそうだとしたらそのきっかけというのを教えていただけますか。
監督:そうですね、すごい個人的な話になってしまうんですけど、25歳くらいのときに、当時付き合っていた女の子がいたんですが、別れて1年ぶりくらいに連絡が来て。ぶっちゃけ僕はまだその時その子が好きだったんですけど。
Q:この質問、やめましょうか?(笑)
監督:いえいえ全然問題ないです、その女の子も知っている話なので。それから渋谷のカフェで会う約束をして、ノコノコと行ったわけなんです。そしたら彼女の隣に女の子が座ってたんです。僕は『え、3人?』って、腰砕けだなって思ったんですけど。話をしていくうちに、彼女の方からカミングアウトしてくれたんですよ、バイセクシャルだって。彼女はそこで、僕と別れた後にその女の子と出会って、付き合っていくうちに自分がバイセクシャルだってことに気づいたってことを告白したんです。僕自身は中学の頃からゲイの友達とかがいたのでそこに驚きはなかったんですけど、僕の目の前でしゃべってる二人の感じが、すごく幸せそうだったんですよね。で、あれ、いいなって思って。僕といるときには見せなかった幸せそうな顔をしていて。ちょっときついんですけど、もう6年以上も前の話なので。そのことがすごく印象に残っていて、そういう幸せそうな2人の顔を撮りたいなぁ、というところから出発して脚本書いたという感じです。
Q:ありがとうございます。それが本当にこんな美しい作品に結実するとは、という印象です。もしかしたらその喫茶店での2人の女性からインスパイアされた姿が今回の2人の女優さんに投影されているのかもしれません。監督は2人の女優さんにカメラを向けるにあたって、どのようなことを注意されていたか、どのようなことを意識されていたかお伺いできますでしょうか。
監督:僕は普段はテレビの仕事を主にしていて、ドキュメンタリーをやらせてもらっていることが多いんですけど、20代の頃はテレビドラマの助監督の仕事もやっていて、書かれた脚本、言葉とか台詞とか感情だったりを、そのまま映画にしていくということに違和感がありました。そういう素晴らしい作品もあるんですけど、僕自身が作品を撮るときにそういう作り方をするのがすごく違和感があったんです。なので2人にカメラを向けたとき、あるいはカメラを向けることで現れてくる感情みたいなものがあったときに、それが必ずしも脚本に即してなくても、そちらを優先したいなっていう思いがすごく強いので。だから演技指導みたいなのは全然していないんですよ。本当に感じるままにやってくれ、としか言わなくて。何回も何回も(同じ場面を)やってもらって。ただ助監督とかやってる頃に(俳優さんに)聞かれたんですよ、『改善点を教えてください、どこをどうしたらいいですか』って。僕は色々答えていたんですけど、何か分からないなって思って。改善点って言われても、僕の中の何かが違うってだけなので、それを言いようがないっていうか。だからそういう意味で言うと、脚本はもちろんあるんですけど、脚本に即するよりも、現場で起こったことをいかに捕まえていくか、という作り方をしていた気がします。
Q:なるほど。表現や台詞も含めて任せてしまっている部分もあるのでしょうか?
監督:脚本のないシーンもあるんですよ。秋月さんが遠藤さんに夜の仕事をしているって言うシーンがあると思うんですが、あのシーンは本当は脚本では「・・・」としか書いていなくて、それを撮りたいがために、これは映画監督の諏訪敦彦さんに教えてもらったんですけど、即興をやるために脚本に書いてある1時間前のシーンを試しにやってみるという。だからその「・・・」のシーンを撮るために、実際ちょっとキャメラアウトしてみようと。そういうふうにやっていたら、それが面白くてですね。キャメラマンの山本くんも面白がって撮ってくれて。で本当は使う予定はなかったんですけど、編集のときに見てたらすごく面白かったので、そのまま映画に使わせてもらったっていう流れです。
Q:この映画はすごく低予算だと聞きましたが、あの雪のワンシーンは、あれは急遽雪が降ったから撮ろうと思って撮ったのでしょうか。
監督:そうですね、みんな仕事をしながら撮影していたので、土日に集まるのは基本僕と撮影の山本くんと録音部の3人みたいな感じでした。あの雪のシーンは実際に遠藤さんがモデルのお仕事をやられていたので、実際に仕事をしているシーンを撮らせてくれとお願いしました。作品に使うかどうかわからなかったんですけど、ちょっと仕事してるところ見てみたいっていうのがあって、(現場に)お邪魔したら雪が降ってたんですよ。行きあたりばったりだと言ったらそれまでなんですけど、僕はそういうふうに映画を撮りたいというか。たとえば最後のシーンも現場に行ってみたら少年がバスケをしていて。
Q:あれは脚本に入れていたのではなかったんですね。
監督:そうなんです。話を聞いてたら『部活でうまくなりたいから練習してる』って言ってて。めっちゃいいなって思って、まずは彼を撮りたいなって思ったんですよ。その場で交渉して、終わったらジュースおごるからって言って、そのままいてもらって。本当は(2人が)見つめ合って終わるって感じだったんですけど、結局2人があてはないけど同じ方向を向いて終わるっていうのをその場で考えて、どう?と聞いたら、みんな首をかしげながらも良いんじゃないって言ってくれたので、そのままやらせてもらいました。僕がお世話になってる「こども映画教室」という、子どもたちと一緒に映画を作るというワークショップで諏訪さんに教えてもらったのですが、「岩の映画」と「レンガの映画」というのがあって、アンドレ・バザンがロッセリーニの映画を擁護したときのエッセイらしいのですが、普通の映画(レンガの映画)がキレイなレンガを積み重ねて向こうに渡る橋を作るようなものだとしたら、岩の映画っていうのは川の向こうに渡るときにその場にある岩を飛び越えてジャンプしていくようなもので、向こうに渡れたときに初めてそこに橋ができるっていうことを言っているらしくて。書いてある設計図通りにやるのはもちろん良いのですけど、僕自身がそういう映画作りにあまり合っていないというか、どんどんジャンプしながら1個シーンを撮った、じゃあ次はどうしようか、というふうに現場で考えながら撮っていきたいなって思っています。
Q:素晴らしいラストシーンだと思いました。でもそれだと監督が常に脚本以上のものに意識を張り巡らせてなきゃいけないので、現場は相当気持ち的にも大変なんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
監督:そうですね、僕もそうだと思います。スタッフは特に、そんなんじゃ撮れないよ、とか、もうちょっとテストしてくれよ、とか、普通はそう言うと思うんですけど、そこは割り切ってというか、信頼してくれていて。僕もキャメラさんとか録音さんのことを信頼してましたし。俳優さんが「もう一回」って言われてすごい怪訝そうな顔したときも「とにかく信じてやってくれ」ってことしか言ってなかったので。
Q:主演の2人は監督自身がこの2人にやってもらうと決めていたのか、それともオーディションで選んだのでしょうか。
監督:オーディションっていうのはあまり信じてなくて。(自分が)映画を見ていて「あ、この人良いな」とか、この人とやってみたいな、というふうに決めることが多いです。秋月さんに関しては『風切羽〜かざきりば〜』っていう映画を、ちょうど僕が脚本を書き終えてそろそろ撮り始めたいなーという頃に映画館で見て、事務所の方に問い合わせたら興味をもっていただいて、やってもらえるってことになったんですね。遠藤さんに関しては、秋月さんの事務所の方に相手役が難航してるんですと相談したら紹介していただき決まりました。なので全然演技とか見たことが無かったんですけど、2人がツーショットで立ってる姿が想像できたというか、良いなと思ったので、直感を信じようという気持ちで決めました。
Q:他の方についてもお伺いしたいんですが。渡辺真起子さんについては今でもインデペンデント界のミューズのような存在でいらっしゃいますけれども、彼女の起用についてはいかがだったのでしょうか。
監督:真起子さんについては、僕がぜひやっていただきたいと思って、脚本の段階からあの役は真起子さんにやってもらえたら良いな、ということで書いていたんです。去年から僕は会社を辞めてフリーでやっているのですが、会社員時代にテレビの連続ドラマでADをやっていたら、真起子さんが出ていて、マネージャーさんと仲良くなったんです。それで今回の映画を撮るときに脚本を読んでいただいて、1週間後にじゃあやりましょう、ということになりました。脚本に興味を持っていただいたのか、前の作品に興味を持っていただいたのかは分からないのですけど、本当にありがたいなって思います。
Q:真起子さんに演技をつけるとか、現場でのやりとりとかはどうだったのでしょうか。
監督:そうですね、けっこう僕、同じシーンを何度もやるんです。ただ真起子さんに関しては「やります」と言った後のファーストテイクが一番良いので、特に何度も繰り返すということは無かったです。ただ演出って僕はあんまりよく分かっていなくて。例えば(司会の)矢田部さんとお話しているときに、ちょっと面白いことを言ってくださいとか言ったとしても、それは僕の思っている矢田部さんの感情であって、矢田部さん自身の感情ではないかもしれないじゃないですか。だから何だかそういうことを相手に伝えるということが全然意味が分からないというか。だから相手の俳優さんが感じたことをいかに映画にするかっていうことを常に考えながらやっています。
Q:この手の作品という言い方をすると大変失礼なのですが、近作では金子修介監督の『ジェリー・フィッシュ』、あとはタイ映画でやはりこうした系統の映画が1本ありまして。金子監督は50代くらいで製作して、タイ映画は確か女性監督で女性目線の作品なのです。今回の作品は若い男性の手によるものなのですが、若い監督だからできたことなどがあれば教えてください。今回の作品は若い方が作った、みずみずしい作品だというのが見ていて分かりました。
監督:すみません、金子さんの作品は見ていないんですが。僕は自分の身の回りのことしか映画にできないと思っていて、僕が例えば50代の離婚しそうな夫婦のことを映画にするといっても、自分自身がリアリティがもてないし、描けないと思うんです。今回の作品は自分と年の近い女の子たちでしたし、モチベーションが出るのは自分の身の回りで起こっていることを映画にしたいというときだと僕は思うので。今回の作品はそういう感じです。答えになっていますでしょうか。
Q:もし20年後に同じテーマで作品を撮るとしたら、今回の作品とどう変わるか、想像だけでよろしいのでお答えいただけますでしょうか。
監督:そうですね、20年後だと、様々な経験を経たから分かることもあるでしょうし、逆に忘れちゃうこともあるんじゃないかと思います。20年後この作品をもう一回見てみたいというふうには思います。
Q:公園に行ったときに、もし少年が居なかった場合に、どう撮ろうと思っていたかというのを聞きたいと思います。
監督:一番最初の台本では、奈々が家に帰ったら、家の前で真凛が待ってたって設定だったんです。ただ撮っていくうちに、それだと二人の距離が近すぎるかなと思いまして、公共の場であったほうがいいんじゃないかと。それであそこの公園に書き直したんですね。台本上では奈々が歩いていって、真凛と出会うくらいしか書かれてなかったんですよ。ホントに現場で考えようとしか考えてなくて。
その場にいって二人がどういう感情になるかわからなかったですし、僕自身もどういう風に感じるかわからなかったので。行ってから考えようという感じだったんですけれども。最後のカットに関しては、さっき演出って言うのが良くわからないと言っちゃったんですけど、これも(他の)監督の言葉なんですが、是枝監督の授業を受けたことがあって、フィクションとドキュメンタリーの違いって言うのは、ドキュメンタリーって言うのは、どこまでいっても二人称でしかない。相手の内面には絶対入り込めない。相手の内面をナレーションで語っちゃったり、その相手の目線に入ることは、ドキュメンタリーとしては成立していないというようなことを言っていて。フィクションの方は、相手の内面に入っていけるということを言っていたんですね。神の視点というか、このときこの人物はこういう風に思っているとか、感情に入っていけると言っていて。ボクはそのことが頭にあったんですけれども、一番最後のカットだけ、彼女に笑ってほしいなと思っていたんですよね。ですのでカメラ目線で笑ってくれと言いました。
Q:『Starting Over』今後の展開も含めまして、次回作の構想も含めて最後一言いただけますでしょうか。
監督:こうして呼んでいただけたのは光栄なんですけれども、自主映画なので配給が全く決まっていません。映画祭を通してどこかの誰かとお知り合いになれたらいいかな、と思っているくらいな感じです。この映画に関しては。次の映画はプロットはもうできていて、やってみたい俳優さんもいて、その俳優さんと話をして、やろうよという話は出てるんで、5年かかるかもしれないんですけど、頑張ってやっていきたいなと思っております。
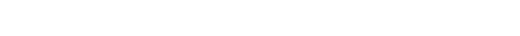


















 Check
Check





