
10/28(火)、日本映画スプラッシュ『Starting Over』の上映後、西原孝志監督、女優の秋月三佳さん、遠藤新菜さん、渡辺真起子さんのQ&Aが行われました。
⇒作品詳細
司会:お客様と一緒にご覧いただきましたが、いかがでしたか。
秋月三佳さん(以下、秋月さん):ひえー。本当にありがたいことですよね!もうほっとしますよね!
司会:スクリーンを見ながら秋月さんが笑わないかとみんな心配して見ています。
秋月さん:本当に。私得意なんですよ、死んだ目で突き刺すというのが。
司会:でも根はこっち(とても明るい)なんですね。
秋月さん:そうです。ハッピーフェイスなので!
西原孝志監督(以下、監督):撮影中もキャッキャッキャッキャッ言っていて
司会:遠藤さんはいかがでしたか?
遠藤新菜さん(以下、遠藤さん):DVDでは事前に見ているのですけども、こうしてスクリーンでお客様と一緒に見た方が2000倍いいね!と、さきほど皆さんと話していました。
秋月さん:本当に!だって家で見たとき眠くなったもん!(笑)
監督:眠くなる映画はいい映画だって、佐藤真さんっていうドキュメンタリー監督が言っていました。
司会:渡辺さんはご覧になってどうでしたか。
渡辺真起子さん(以下、渡辺さん):若いっていうのはやっぱ乱暴ですね!とは言いながら、ドキドキそわそわしながらやらせていただきました。私は私で私なりに、うわ、自分の芝居、って。こんなことして失敗したな、とか。いたたまれないというか、慣れないというか。自分の参加した作品を見るのをあんまり得意ではないので。出てくる度に「チッ」(舌打ち)っていう。その場では一生懸命やったのですが、やはり恥ずかしいです。あと二人がとても瑞々しくて。あとすごく客観的に「このお母さん酷いな!」という。
司会:監督は、脚本から作っているのですが、この「やり直す」というタイトルの映画を作ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
監督:最初の上映があったときにも話したのですが、最初のきっかけは25歳くらいのときに、当時付き合っていた彼女がいて、別れて1年ぶりくらいに連絡がきたんです。僕はぶっちゃけまだ好きだったので、連絡来たか、と思って、渋谷のカフェにのこのこ行きましたら、彼女が座っていて、隣に女の子が座っていて「あ、3人」と思って。話を聞いていたら、彼女がカミングアウトしてくれて「いま、女の子と付き合っている。」って感じだったんです。僕自身は中学生くらいのときからゲイの友達とかいたので、驚きはなくて、すんなり受け入れられました。でも、僕の目の前にいる二人がすごく幸せそうだったんですよ。それでその表情がちょっといいなぁって思って印象に残っていました。それでその女の子ふたりで、お互いにお互いを信じ合っている二人ということをずっと思って、25歳くらいのときに、脚本をばーっと書いて。それがずっと残っていて、それを直しながら。それで去年自主映画なんですけども、ようやくお金の目処がたったので、自分たちで撮ろうかなぁと思ってやった次第です。

司会:失恋してショックでもあったんですよね、一応。
監督:そうですね。その話、します?まだ(笑)?全然良いのですけど。今も仲いいんで。本当に何があるかわからないですね、人生。
司会:では、どなたかから質問を受け付けたいと思うのですが
渡辺さん:はいはいはいはい!二人は割と長い期間撮影して、一緒に作品を作っていたと思うんだけども、割と生っぽいというか、何かこう、いわゆる「お芝居をします!」という風には撮らないじゃないですか、監督が。二人はそれをどういう風に受け入れたの?だいたい現場で(監督の)声が小さいじゃん。

監督:そうですね。自分で言うのもなんですけど。いつスタートを言ったのかわからないって。
渡辺さん:本当に重要なことなのに、本当に声が小さいんです。だから段々みんな、ひそひそ話になるっていう
司会:集中した現場だったんですね。
遠藤さん:どうだったかね。三佳だったからこそ、っていうのはありました、私のなかで。
秋月さん:ありがとうございます。私もです。
司会:この映画で初対面ですか?
遠藤さん:共演は初めてでした。面識はあったのですが。なので、二人で話をしたり、特に現場で空いている時間などのコミュニケーションなどは、意識的にイチャイチャしていたと思います。無意識なんですけど。ふたりとも自然に入り込んでいたからこそ。なんか、撮影のないときにもすごい連絡をとっていたり。

秋月さん:監督のことも信じていたけれど、一番(遠藤さんを)信じてやっていました。

渡辺さん:それは見ていて分かった。なんかいいな。私も負けてられない、みたいな。
司会:監督はこのお三方をどうしてキャスティングされたのでしょうか。
監督:そうですね。(渡辺)真起子さんに関しては、元々脚本を書いている段階で、やっていただけたらいいな、という夢物語的なことで、書いていました。
司会:当て書きでしたか?
監督:そうです
渡辺さん:別に私、あんな人じゃないですからね!(笑)
監督:元々、諏訪さんの『M/OTHER』(諏訪敦彦監督)を最初に見て、それで大ファンだったのもあるんですけれども。それで秋月さんは、『風切羽~かざきりば~』(小澤雅人監督)という映画がありまして、それを、たまたま脚本を書き終わって準備をしている段階で、池袋の映画館で拝見しまして、いいな、と思って事務所の方に、こういう監督の自主映画なんですけれども、と相談したら、興味をもっていただいて、やっていただけることになりました。遠藤さんは、それで、こういう(同性愛の)映画なので、相手役がなかなか難航していたときに、秋月さんの事務所の方からご紹介いただいて、それで写真を拝見したときに、秋月さんと並んでいる2ショットがイメージできたというか。いいな、って思ったんです。それでお会いしてみたら、こういう感じの明るい面白い子だったので。お芝居とかあんまり見たことなかったのですけれども、決めてしまいました。僕自身はあんまり、さっき真起子さんもおっしゃっていましたけど、芝居というのはあんまり信じていなくて。
渡辺さん:人は信じたいのに芝居は信じたくないわけね。ドキュメンタリー畑(監督はドキュメンタリーのTVディレクター)だし、っていうのもあるしね。
監督:自分が今やらせてもらっている、というのもあるのですが。ジョン・カサヴェテスという映画監督の言葉で「登場人物というのは信じていなくて、登場人物を誰かが演じたら、その役はイコールその人間なんだ。」みたいな。うろ覚えですが(笑)その役を誰かがやった瞬間に、例えばその役を誰かがやった瞬間にその役は、例えば秋月さんだったり、遠藤さんだったり、真起子さんだったりするっていう。だから演技指導というのもあんまり僕は分からないですし、感じるままにやってください、ということだけを言っていた気がします。
司会:二人はタフなシーンもあったと思いますが、どうしてこの映画を受けようと思ったのでしょうか。
秋月さん:私はレズビアンの映画大好きで。シャーリーズ・セロンの『モンスター』がすっごく好きで、こういう役絶対やりたい!と思っていて。ああいう役ではないけど、レズビアンってすごく純粋だし、それを表現することに憧れがあって。それで台本を読んで「うわ、これはいきたい!」って思って、やりたいと思いました。
遠藤さん:私もこれが特に好き、というのは無いのですけど、単純に自分の中で同性愛が結構身近だったりするので。周りの環境だったりとか。海外とかだったらもうちょっとラフに取り上げてもらえる問題だと思うのですが、日本だとヘビーに考えがちというか。自分はハーフなのですが、日本ではそういう映画に触れてもらえる機会があまりないと思ったし、自分が関われるのだったら是非、と思って参加させていただきました。
司会:渡辺さん、自分はああいうキャラではないとおっしゃいましたけども。
渡辺さん:適当なことを言いまして(笑)一度、西原監督と別の現場でお会いしていたのですが、基本的には、これでやっていくぞ、という決意のある方とできるだけご一緒できたらな、といつも思うんです。題材は題材なのですが、そこに余計な偏見がない映画で。私自身もそういうものに対してまったく偏見がないし、彼女たちが言ったように、そういう風に生きるひとたちを出来るだけ肯定したいなと思うし、色んなバリエーションの中、色んな生き方の一つで自分も生きているな、というのを自分も表現できたらいいなと思っているので。そのあたりはゆっくりお話して、大丈夫だろうな、と。
司会:お母さんのキャラクターというのは、どうしてああいう設定にされたのですか?
監督:強い人間はいっぱいいると思うのですけれども、僕は強い人が苦手というか。日常生活でもそうですけども。どこかに弱いところを、人間誰しも持っていると思います。そういう弱さを見せてくれる人を信頼できる、というのがあるんですよね。
渡辺さん:ごめん、ちょっと笑っちゃった(笑)
監督:いいこと言ったつもりなんですけども。真起子さんも、渋川さんも、(台詞を)言い終わった後に、その弱さを見せてくれるというか。だから、編集でああいう形で使わせていただきました。
渡辺さん:今日客観的に見ていたら、とりあえず、ダメな人ばっかり出てくるなと。
Q:全編を通じて、ハンドカメラの揺れが良い味付けになっていたのではないかと思うのですが、狙いがあったのかということを監督にお伺いしたいです。ご出演されたお三方には、監督が、脚本よりも役者さんの表現を大事にされるとおっしゃっていたので、役作りよりも、これは自分の素に近い演技だというシーンがあればお教えください。
監督:そうですね、2つあります。1つは、僕のやりたい方法は台本に沿ってもらうというよりは、自由に動くというものなので、手持ちの方が追いかけやすかったということです。
渡辺さん:割と手法としてこういうタイプと言うと大雑把なのですが、元々芝居がうまくないので、そういう演出を受けることが多めなんです。役作りって難しいのですよね。ステレオタイプに入ってしまうと、私がやる意味がなくなるんじゃないかと、どこか抵抗してしまう。何割かを自分の身体、何割かを物語に委ねるという形ですね。だから素がどうか、というと、撮られ放題の手法の映画では、「もうこのアゴ!」とか「うかうかしている背中!」とかが素なんじゃないですかね。最後娘役が、バックショットで緑色のパンツをはいて歩いていたときに「やばい歩き方が似てる!」とか。親子って。駅の帰りのシーンでは、私男だったかなってくらい、ゆるーって自分の身体で歩いているなっていう気がして。そういうのが素ですね。彼女が同じように歩いていたから「ああいいんじゃん」って(笑)やっぱ逃れられないですね。自分というものからは。
遠藤さん:二人のシーンだと、例えば奈々が、バイトのことを言う、かみ合っていない会話のシーンとか、そこはもう完全にアドリブで、台本に台詞はありませんでした。
秋月さん:20分撮ったんです。私がそのバイトを言うって、伝えるということだけが決まっていて。でも全然言えなくて。
渡辺さん:フィルムだったらアウトですよね
遠藤さん:長回しが結構あって。例えば、泣いているシーンとかも20分くらい泣き続けて。それを4テイクくらい。
秋月さん:それもどんどん成長していって。1テイク目は、2人とも赤ちゃんみたいに、わけがわからない喧嘩になって。でも5テイク目くらいには、どんどん冷静になっていって。お互い気持ちがまとまってないけど、言いたい事はこうだ、みたいな最初の方のカットが使われていると思います。
遠藤さん:だからほとんど自然体でした
渡辺さん:やっていて、やだもうこの監督っていう風には思わなかったの?
遠藤さん:それは信じていました
秋月さん:一番初めに台本を読んだときから、あのシーンはすごく泣いてしまっていて。あれが泣いたのがいいのか悪いのかはわかりませんが、あのとき出たものだから信じるのですけど。
遠藤さん:(その時は)好きすぎて。でも正解なのかな、と。ラブシーンとかは本当に恥ずかしかったです。見ていてどうしようと思って。
秋月さん:初のキスシーンを捧げたんですよ。遠藤新菜さんに。もっとイケメンの俳優さんに捧げたかったのに(笑)
渡辺さん:監督ちょっと、突っ込んでくださいよ。
監督:本当に(現場でも)こんな感じで。思い出したので、さっきの質問答えますね。例えば、秋月さんにも遠藤さんも、単純にただ向こうに歩くというときにも、あの花が綺麗だな、とか風が気持ち良いな、とか感じるじゃないですか。ですから、お芝居の途中でも何か感じることがあったらそっちを感じてくださいって言っていたんですね。バスケが終わってベンチでじゃれあっているとき「あ、シャボン玉」って言うショットがあるんですけど、あれは本当に後ろで誰かがシャボン玉をやっていたのに気付いて、カメラマンに頼んでそのシャボン玉を撮ってもらったりしました。奈々が見た風景とか、見たかもしれない風景とか、新菜ちゃんが見たかもしれない風景とかは、カメラマンと相談して積極的に撮っていました。
司会:喧嘩の途中に靴下をもじもじするところとかも?
監督:あれは二人に自由にやってもらって、山本さんに自由に撮ってもらって、僕はほんと、カメラの横で「いい映画撮れますように」って拝んで。状況をつくって、説明して、スタートって言っちゃったら、本当に無力、というか。監督って本当にやることないんですよね。それで編集で、初めて見て、くつしたもじもじいいな!と思って。だから最後まで使ったんですけど。
Q:このタイトル、英語のタイトルになっているのですが、これはなにかインターナショナルなセールスを意識されたのか、ポスターのヴィジュアルはどういう意図でこれにされたのか聞きたいと思います。
監督:僕は割と出来上がってから、どういうタイトルかなと思うタイプでして。出来上がったときに単純に『Starting Over』という言葉がしっくりきたので、使いました。
司会:やり直すという台詞は監督としては、後半はキーポイントになっていたと。
監督:そうですね、やり直す、人を信じるっていうのは。僕らの世代は、昔通じていた、国家とか政治とかの大きな物語が信じられるものとしてあったと思うんですけど、それがなくなっちゃったと思うんですね。3年前の震災以降、誰も信じられないみたいな世の中だと思うんです。そんなとき、隣にいる友達とか、愛する人とかを信じることから始めたいなとは思っていて、そういうことからタイトルをつけました。ポスターは、山本くんにスチールカメラを持ってきてもらって、撮ってもらった写真で。いい写真ですよね。
司会:2ショットではなくてバラバラのイメージ?
渡辺さん:基本的にフレームの中に2人もしくは3人くらいまでだもんね
監督:一昨日も言ったのですけど、最後のシーンは公園で再開して終わるというシーンだったのです。でも公園に行ってみたら、少年がバスケをしていて。それを見て、なんかいいなと思って。それで皆と話し合って、二人が出会うって最後よりも、同じ方向を見ているというラストがいいんじゃないかなということで、そういう風になりました。
渡辺さん:それまで近すぎるくらいまで向き合ってばかりいますからね。そこから後半、解放されていくんだなと。ちょっと幸せでしたけど。
Q:真凛ちゃんの家族背景があまり語られていなかったのですけども、監督のほうではイメージはあってそれを伝えたのか(演技指導したのか)というのと、遠藤さんはどういうイメージで演じられたのかというのをお聞きしたいです。
監督:カフェのシーンでちょっと話していたのですが、両親が若くして亡くなって、そのあと引き取られたおばあちゃんも亡くなって、ひとりきりで暮らしているという設定でした。秋月さんにもですが、まったく演技指導はしていないです。役者さんも脚本があって感じることがあったと思って、僕が「こういう風にしてください」と言ってもそれは僕の考えであって、遠藤さんがどう考えているかはまた違うわけですから。それを僕が考えている方向に調整していくという作業があまり好きではなくて。感じたままにやってくださいと言っていて。あまりにも外れすぎて作品が壊れてしまうと思ったときには言いましたけど。基本的には二人の事を信じてやっていただきました。
遠藤さん:最初はどういう設定なんですか、と聞いて。どういう心情でやったらいいかわからないですって。でもだんだんあんまり背景にこだわらなくてもいいのではないかって。どうでもいいのかな、と一回思って。それも役者としてはどうなのかなって感じなんですけど(笑)。多分真凛は家族を失って辛い部分も奥底にもあるんですけど、バスで、お母さんの名前をつぶやいちゃうところとかで出ていると思うのですが。でも目前のことの方がしっかりしているんだな、と思ったので。意外と自立しているこの子と向き合ってやろうと思いました。家族ということよりも奈々と自分がどう向き合うかってことに集中して役作りしていたつもりです。
Q:では最後に皆様一言ずつお願いします。
秋月さん:こんなに自由に演じさせていただいたのは、役者としても嬉しい事で。時間をかけて作ったので。またこうやって時間をかけて作る作品をやってみたいな、と思います。でもすごくしんどくて、大変でした。ストレス過多って感じでした。それでだんだんただの好感のもてないブスみたいになっていく感じが奈々という感じで良かったのではないかと思って、自分では納得しています。そしてこの映画を公開させられるような女優になっていきたいと思います。
遠藤さん:こんなに時間をかけた映画で、私ごときの女優に自由にやってくださいって言ってくれる監督さんもなかなかいらっしゃらないので。一緒にやることができて、初めて身体をはったかな、援助交際とかラブシーンとかもあって。もっとできるかもしれないって希望を持たせてくれて。
秋月さん:これから、挑戦的な映画にどんどん出たいと思っております。
渡辺さん:わたしはこれから、そうですね、今舞台の公演中で声がガラガラなのですが、20代の頃は夢も希望もあったのですが、途中から成り行き任せみたいな人生なので。私は映画制作というか、物語を紡いでいくようなことが大好きなんです。それは物語を通じて人を知る事をできるというか。なにかを信じ直せたり、信じられなくなったものを取り戻せたりとか。考える事がもう一度できたりとか。だからきっと、お客様に届いたときに、見てくださった中にもそう感じる方がいらっしゃるんじゃないかな、とか。だから、そのやりとりがあるうちは、まだ世界を信じてもいいのではないかな、とか。こんな年になってきたので、これから先は仲間のため、何かをしたいという人のそばにいれたらいいなと思います。
監督:自由って難しいのですよ。好きにやってくださいと言われても、分からないよ、となっちゃいますし。カメラマンにもリハーサルなしでいきなり撮ったりとか。それどう撮っていいの?と普通なっちゃうんですよ。でもそのなかで、僕のことを信じてやってくれたのは、ありがたかったなと思います。個人的には映画の監督、王様というイメージがあると思うのですが、僕はそういう強い監督には全然憧れなくて、積極的に弱くありたいというか。本当に役者さんとかスタッフさんとかと話し合いながらひとつの作品を作るというのが楽しいので、これからも、そういった作品を作りたいと思っています。

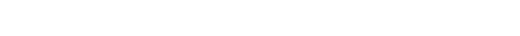


















 Check
Check





