
左からジョシュア・サフディ監督、ベニー・サフディ監督、アリエル・ホームズさん、ケイレブ・ランドリー・ジョーンズさん
10月28日(火)、コンペティション『神様なんかくそくらえ』の上映後、ジョシュア・サフディ監督、ベニー・サフディ監督、女優のアリエル・ホームズさん、俳優のケイレブ・ランドリー・ジョーンズさんのQ&Aが行われました。
⇒作品詳細
ジョシュア・サフディ監督(以下、ジョシュア監督):東京国際映画祭で2度目の上映なのですが、なんだか初めて上映した気分です。とても光栄に思っております。日本の方々は極端なものについての理解度がとても高いと私たちは思っているので、特に光栄に思います。

ベニー・サフディ監督(以下、ベニー監督):僕たちは兄弟で一緒に仕事をしているので、よくこのような事があるのですが、一人の方が喋っていて、もう終わりなのかなと思っていると、いきなり話を振られて。今回もいきなり振られた感じがしたのですが。日本の方々に対して、非常に尊敬の思いがありますので、このように日本で上映出来ることをとてもありがたく、特別なことだと思っています。使われている音楽は冨田勲の音楽なのですが、そこでも日本とのコネクションがあります。

アリエル・ホームズさん(以下、アリエルさん):私もこの映画祭に呼んでいただき、とてもありがたいと思っております。そして、このような形で日本にいられること、映画を上映できることを本当に素晴らしいと思っております。みなさんにこの映画を楽しんでいただけたらと思います。

ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ(以下、ケイレブさん):日本に来られてすごく興奮しています。皆さん、どうもありがとう。

司会:先ほど、控室で全員そろったのですが、ケイレブさんが映画とは全く違いこんなに美しい人だとは思わなくて、同じ人かと目を疑いました。
ベニー監督:ニューヨークで上映した時に、ケイレブもステージにいたのですが、お年寄りの女性が「あの男の子誰?」「なんであそこにいるの?」と言っておりました。
ジョシュア監督:彼はカメレオンのようなところがあるのですが。(ケイレブに向かって)最初に君と話をした時かエ-ジェントと話をした時か分からないのだけど、僕がこう言ったんですよね。「この作品のケイレブは、今までの映画の中で最悪に見える」と。でも、美しい方ですよね。
司会:作り手の方々はこのように陽気な方達なのですが、映画はとても深刻です。これは、アリエルさん自身がこのオリジナルストーリーをお書きになって、それを映像化したということでよろしいですか?そして、俳優さんたちと、どのようにしてこの書かれたものを形にしていったのでしょうか。
アリエルさん:そのストーリーというのは、実は私の実際の生活、過去の3年間にわたるメモワールというか、自伝的な話です。
ジョシュア監督:この映画を作るために彼女に自分の体験を書いてほしいと頼みました。そしてその出来上がったものが非常に詳細にわたっていました。私と一緒に脚本を書いてくれたロナルド・ブロンスタインが、それを脚本にしていったのですが、なるべく原作に忠実に、特に感情的なものと気質的なものはもとの手記に忠実にしようと思いました。撮影をしながらアリエルは何度も「これはこういうふうに怒ったんじゃない」とか、「これは事実とは違う」といったこともあったのですが、私たちは何度も彼女に説明したんですね。というのは、そのときの感情を伝えるにはもう少し、出来事を強調した方が良いんだということを何度も言いました。そのときの感情というのを出したかったんです。
Q:映画を観て凄く印象に残ったのが、クローズアップの対応と背景をかなりぼかして捉えていたと思うのですが、これに意味があれば教えて下さい。
ジョシュア監督:チャレンジというか、美しさだと思うのですが、ストリートのドラマというのは、実際にストリートで起こっていることの美しさというのは、外なので、色々な人に囲まれているのだけれども今現在には自分と自分の心と相手とその感情しかない、ということなんですね。それを表すのにこのクローズアップというのはシネマ特有の使い方なんだと思うのですが、凄くいいと思いました。物凄く遠くに居るのだけれども、すごく近いということを表すために、背景がぼやけていてクローズアップというのを表したかったんです。それはすごく主観的な面を表そうと思っていたのですが、この映画のコンセプトというのは公共の場ですごく主観的であることだったんですね。公共の場には主観性というのはないのですが、そういう場で主観的であるということをコンセプトにしました。そして映画の中では「パワー・オブ・ザ・マインド」という、ヘッド・ハンターズというバンドの曲が流れているんですが、まさにそのマインドの力というものを表したかったんです。
ベニー監督:観た人がよく「これはドキュメンタリーかと思った」とか、「すごくリアルな感じがして、ドキュメンタリー的だね」と言われるんですが、たぶんそれはクローズアップを多用しているからなのかなと思うのですが、実はこれはとても大変なんですね。5ブロックとか10ブロック離れたところからズームアップをするというやり方をしたのでとても難しいんです。いろんなことをきっちり作り込んでいかないとこういう画面が撮れないんですけれど、という意味で、ドキュメンタリーと正反対の作り方なんですけど、感じ方としてはドキュメンタリーのようなタッチに感じられるということなんですね。つまり脳がそういうふうに受け取るということだと思うのですが、そういう意味で非常に逆説的な感じがします。遠くに離れれば離れるほど、より近くに感じられるというパラドックスがあるのですが、まあちょっとドラッグみたいな感じですね。
Q2:映画の中でダンキンドーナッツであったりマクドナルドであったりバーンズ・アンド・ノーブルなどの固有名詞が出てきたのは、何かこだわりがあったのでしょうか?
アリエルさん:ああいう場所というのは、実際に私とか、映画のキャラクター、じつは私の本当の友だちなのですけれど、登場人物たちがぶらついていたところなんですね。よく出入りしていたところで、それは暖をとったり何かを飲んだりというために、ああいったところでよく落ち合っていました。
ジョシュア監督:アル・ゴールドスタインという方がいらして、彼は、いったんは億万長者になったんですけれど、そのあとホームレスになった方で、彼が自伝の中で言っていたのが、最も偉大なシェルター(逃げ場)というのが、アメリカの大きな会社が作ったものであると。それはマクドナルドであったり、スターバックスであったり、バーガーキングであったりで、そういうところにホームレスの人たちが避難所としてよく出入りしていて大変ありがたかった、というふうに言っています。
Q:先ほどパラドックスの話がありましたけれど、やはり僕たち東洋人にとっては神という概念には馴染みが薄いのですが、ただ私は年をとったせいもあって、最近よく神とは何だろう、誰だろうということを考えることがあります。結局私のイメージとしてあるのは、神といえば無限のものであり、永遠のものであり、事実的な存在であり、必然的な存在であると捉えていますが、そういう観点からいきますと、たとえば永遠の存在といった場合、時間ではないわけです。ですからもし現実が、時間が流れている世界であるとすれば、どうしても時間の中に神は永遠としては現れることができないという、これもまた1つのパラドックスを提示しているんではないかと思うわけです。したがって、今日の映画で私に教えられたことは、絶えず、ある意味で惨めで残酷な、あるいは狂気じみたこの現在というところから、どうやって逃げるかといった場合、やはり永遠のほうへ行くしかないんだろうとも思います。だけれども、その永遠の方へは、我々は死ぬしかない、死ななければいけない。そういう意味では、神は存在する、されど神は現実には存在しないというパラドックスがあるのではないかと、この映画を観て思いました。
ジョシュア監督:(日本語で)「どうもありがとうございます。」
ベニー監督:すばらしいです。おっしゃったとおりだと思います。
アリエルさん:私は今おっしゃった方が、どうしてパラドックスについてお話しなさるのか、ちょっと分からないのですが、『神様なんかくそくらえ』という日本語のタイトルだからなのか、あるいは映画の中に登場する人たちがものすごく死に近い存在だからなのでしょうか。
Q:それに対する私なりの答えを申し上げれば、我々の生はいつでも自己矛盾に満ちている一面があるのではないかと思うわけです。その自己矛盾を自己矛盾として捉えてしまえば、ある意味で、この世界では意味がなくなってしまうのではないかと。それにもかかわらず我々は生き続けるというのはどういうことなんだと、それを考えたときに、やはりその自己矛盾を自己矛盾としてではなく、違った、いわゆるパラドックスとしてむしろ取り上げないと自己矛盾を乗り越えられないというか、どうしても自己矛盾から我々は脱出できないのではないかと。だから今まで言われてきている色々な意味での歴史的な、あるいは哲学的な言説、あるいは神学的な言説を含めて、そういうものを全部もう一度パラドックスから見直して新しい意味とか、新しい価値とか、新しい思考とか、創造的に新しく作り直していかなければならないんじゃないか、というところで私は言っているわけです。そういう意味では、日本であろうと、アメリカであろうと、他の国であろうと、みんな自己矛盾を抱えている生を引きずって生きているという意味では、パラドックスという問題は至るところにあって、それをこの映画は見せてくれたのではないかなと私は感じたわけです。
アリエルさん:おっしゃった哲学は非常に美しくてすばらしいと思いますし、まったく同感です。この映画の中でのパラドックスというのは、内なる平和を求めていて、そしてこの時間から超越したいと思っているのだけれども、結局あるやり方を通してそれを得ようとするのですが、そのやり方を使ったがために逆に時間に閉じ込められてしまっている、自分たちをこの世の監獄のようなところに閉じ込めてしまっている、というところがパラドックスなのだと思います。
ジョシュア監督:少しつけ加えると、ここで言っている神というのはギリシャ神話の神のことで、つまり不死の神で、死なないということは非常に退屈だと思うんですね。永遠といっても、その永遠の長さの中で何をするんだと。終わりがないというのはある意味で呪いなんじゃないかというふうに思いました。ちょうどこの映画のようで、つまりこの映画には終わりがないのですね。映画は止まりますけれど、終わりがないということです。登場人物たちは、ギリシャ的な意味での神のようにふるまいます。時間の概念がなくて、自分たちの存在を物語で埋めざるを得なくて、そのドラマの中で生きています。ちょうどギリシャ神話の神たちが人間のドラマを作り上げて楽しんだというようにですね。じつは今おっしゃったようなことを、私たちは初めて観客の方から伺ったのですが、私たちが意図していたことをまさにズバリと言っていただきましたので、嬉しく思います。当初の脚本では、凝縮した時間の性質とか非存在とかいうことについて考えていたので、非常に心強く思います。
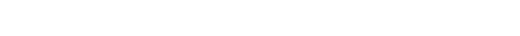


















 Check
Check





