
左からグラディス・ンさん、リャオ・チエカイ監督、エシュリー・ガオさん
10/29(水)、アジアの未来『あの頃のように』の上映後、リャオ・チエカイ監督、女優のエシュリー・ガオさん、脚本のグラディス・ンさんのQ&Aが行われました。
⇒作品詳細
司会:リャオ・チエカイ監督です。そして主演のペイリンを演じましたエシュリー・ガオさん。そして脚本を監督と共同執筆いたしましたグラディス・ンさん。実はこのチームはほぼ通訳がいらないのです。ということで、日本語で何か言ってもらいましょう。監督。
リャオ・チエカイ監督(以下、監督):(日本語)「ダメです。ダメです(笑)。」
司会:ダメですか。青森はどうですか?
監督:(日本語)「楽しいです。」
司会:寒いですか?
監督:(日本語)「寒いです。」
司会:りんごはおいしいですか?
監督:(日本語)「りんご、おいしい。超ヤバイ。」
司会:実は、監督はかつて日本語を勉強していて、ちょっとブランクがあったのですけれども、今は青森に住んでいます。1ヶ月半居てあともう2ヶ月居るということで。それはアーティスト・イン・レジデンスのプログラムですよね。
監督:実は、ACAC青森コンテンポラリーアートセンター(Aomori Contemporary Art Centre〈国際芸術センター青森・ACAC〉)、こちらのアーティスト・イン・レジデンスのプログラムで一ヶ月半で16ミリの作品を仕上げまして現在展示が始まったところですので、これから2ヶ月間、12月14日までですので、青森に行かれるという方は是非ACACにお寄りください。

司会:そして主演を務めましたエシュリー・ガオさんからも一言お願いいたします。
エシュリー・ガオ(以下、エシュリーさん):(日本語で)「初めまして。エシュリーと申します。今日はお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。」

司会:エシュリーさんはいつごろ、どれくらい日本にいらしたのですか?
エシュリーさん:(日本語で)「2011年に交換留学で日本に来ました。」
実は、キャスティング、オーディションとともに脚本の執筆が進行したので、それぞれの得意分野を生かして、例えば「彼女日本語が得意なんだ。じゃあ、日本語通訳」とか、そういうふうに脚本を進められたということと、もう一人の主演の方がいらっしゃいますよね。シェリル・タンさん。シェリル・タンさんも実は歌手だというのが分かって歌手という設定になったんです。シンガーをキャスティングしたために歌手という設定になりました。
Q:素晴らしい作品をありがとうございます。監督と脚本の方にお伺いしたいのですが、この作品を作るにあたっての経緯、どのようなことからこの脚本、この物語になっていったのかというところを教えてください。
監督:実は、僕は短編映画をまず手がけたんですね。「第2話:明日の歌」。これは短編映画として当初撮りました。僕の小学生時代の思い出を振り返って撮ったのですけれども、もしかしたらこれはより拡張して大人のストーリーも書けるかな、と思って書き進めました。その過程でそうするにあたって、グラディスさんに参加してもらって共同で執筆を手がけました。というのも、グラディスさんはスクリプト・スーパーバイザー、脚本を書く上での、何と言うのでしょう、指導担当というようなこともしていらっしゃって、ロケハンのマネージャーもしているので、脚本を各段階で入ってもらったらいいなーということで参加をしてもらいました。
グラディス・ンさん:私が参加した時に、かなり監督はコンセプトとして大きなものを持っていました。将来のパート、大人になったストーリーを考える時に実際に撮影が行われたセント・ジョーンズ島、これはシンガポールの南にある島なんですけれども、こちらに行ったところすごくこの町の雰囲気があって、ここだったらストーリー展開ができるな、ということでちょっとそこに滞在して一緒に書き進め、帰ってからも書き進めました。

Q:BGM、音楽がなんとなく不安を煽るというか、不安な感じの音楽だったり、飛行機が通る音・戦闘機が通る音がすごく大きかったり、劇中に出てくる歌われる歌がいくつかありますが、それが「ブンガワン・ソロ」だったりと、わりと懐かしいホッとするような音楽が使われてて、そこの音楽の対比、音の対比っていうのは何か意図されたものがあったのかどうかを教えていただきたいと思います。
監督:サウンドデザイナーのリン・ティンリーさん、彼女はシンガポール人でイギリスに住んでいる方です。彼女とは以前も仕事をしたことがあって、彼女が知っている作曲家を紹介してくれました。3人で音楽については考え、3つテーマをそれぞれ作ったんです。第1話、若者が更正施設に居るという設定ですけれども、行進したりとかそういうことをしていて。実際これは、このセント・ジョーンズ島の歴史をある意味なぞらえたものです。50年代には政治犯を隔離するための施設がありました。シンガポールに移住する人の移住前の検疫の施設というのもありました。のちには麻薬なり薬物中毒者、更正施設となったものもありました。つまり、人を隔離する場所だったという過去を反映するために、どこかザワつかせるような、おっしゃったような不安定な気持ちにさせるような要素を詰め込んだのです。例えば、何か声が聞こえるとか。夜、行進をしているのにそういう絵は見せるけれども、行進している足音は聞こえない。つまり、幽霊が歩いているような、そんな効果も醸し出しました。そして、おっしゃたように摩天楼が見えますよね。これ2番目のテーマなのですが、これは僕のセンチメンタルな部分。最近の15年で色々なものが変わりました。人々、風景、景色といったもの。なので、そういった変わってしまったものへの郷愁といったものを反映したいと思いました。それはグラディスさん、他の人と一緒にロケハンに行ったときに感じたことですけども、海を挟んで摩天楼を見ると、まるで摩天楼が怪獣のように見えたんです。モンスターのように。というのも、これはレーザーエフェクトみたいのでやっているので、そのライトアップで怪獣映画のように見えたのです。これでまた不安感を掻き立てる音楽をつけました。そして、質問の最後の部分にお答えすると、島で音楽を演奏していた、披露してくれていた島の方々。実は、引退をした俳優の方なんです。今は何をしていらっしゃるかというと、高齢者施設などを慰問して回って一緒に歌を歌っています。そこで歌っている曲を彼が示唆してくれて、それを映画の中で使いました。シンガポールの歌というよりは、インドネシアの曲などが多かったです。ご指摘の「ブンガワン・ソロ」もそうですし、あともう一曲もインドネシアの曲です。
Q:ペイリンとグオフィの間に少し距離を感じました。「人は変わる」というふうに監督が今おっしゃったように、変わって、裏切りというか、そういった変わってしまったことへの裏切り行為というのを反映するために2人の距離が生じたのでしょうか?
監督:まさに今、ディスタンス、距離という言葉を使われましたけれども、それはこの関係を表すのに適切な言葉だと思います。それはこのカップルの2人の距離、物理的な距離ということも1つありますし、過去との繋がり、過去との間に生じてしまった距離ということ。国の変わってしまった姿への郷愁、センチメントといったこと。あと、何か親しみを感じるとか、何か属する気持ちを失ってしまった欠乏ということも示しています。あと加えたいのが、グオフィとペイリンが距離が生じてしまったのは、彼が他の女の子、もう一人の子に気が移ってしまったとか。浮気ではなくて、人間、変わるのが自然な姿ですよね。例えば、大人になるということでも変わりますけども、子ども時代に当たり前に思っていたことがそうではなくなった。そういうことを示しています。
Q:水の表現が多かったと思うのですけど、スイミングとかプールとか、水の表現に対して監督自身、どういった思いで作られたのでしょうか。
監督:グラディスと一緒に脚本を書いていて、最初は別に意図したわけではないのです。水のモチーフを使うとういうのが。ただ気付いたら、水と関わる映像がとても多かったです。例えば、切手を水の中で剥がすとか、そういうのもそうですし。おっしゃったように、泳いで島まで渡るとかそういったことです。水を使ったシーンが多いなということに気付いて、じゃあ逆にちょっと水ということに着目してみようと思いました。あと、音楽をうまく取り込むということ。その一部にするということで、作曲家の人もモチーフとしての水を考えてくれて。コップに水を張ってふちをなでて音を出しますよね。そうすると、ちょっとキーンとした音が出るのですけれども、それを生かして、先ほど音楽の話が出たときに言わなかったのですが、3つあるテーマのもう1つのテーマというのが、この音響効果によって出るものを生かして、ペイリンとグオフィの関係を浮き彫りにするテーマに使いました。
Q:シンガポールは多人種国家ということは理解しています。マレー系の人がいたり、中国語を話す方がいたり。マレー語、中国語、英語がこの劇の中に入っていましたよね。ペイリンともう一人の歌手の彼女が話していた時に、中国語で聞かれて、返した言葉が違ったと思います。それは例えば、葛藤とか、この島にいて隔離されている、ペイリンが島にいて本島から切り離された、というのを表現しようとしたのですか?
監督:実は、その指摘されたシーンというのは、ペイリンが日本語の小説を読んでいて、「なんの言語なの、そのあなたが読んでいる本は?」というので「日本語」というようなことが出てきた部分だと思うのですけれども。シンガポールが多言語、多人種の国だというのを強調したかったわけじゃないというか、あまりに僕たちにとって当然のことなので逆に言うと、英語だけ中国語だけマレー語だけ、というふうにするととても不自然なんです。チャンポンで話すのが普通なんですね。例えば1つのセンテンス(文章)の中でも。なので、シンガポールのテレビ局、テレビはすごく不自然なんです。言語が局で分かれていますから。だから、それが僕たちのアイデンティティの一部だし、そうやってチャンポンで話すことが多様性を表していると思います。自分でもなにか書いていたりして、中国語、マンダリンって言いますね。基本は北京語なんですけれども、東南アジアで話されているマンダリン、なにか1つの言語だけを使うと、何か強調しているんじゃないかとか、あるいは、他の言葉を、多文化を反映してないんじゃないかとか。そういうことを、映画を作る際には考えさせられることです。どういうふうに言語を使うか、というのは。
Q:今回この作品は、監督が普通に話すような感じを想定して書かれた脚本ですか?
監督:例えば、この子ども時代を描いた第2話では、僕自身の子ども時代は基本、中国語系の学校に通っていたので、マンダリン、中国語を喋っていたので、本来男の子は中国語を喋っている、という設定で脚本を書きました。キャスティングで今の小学生をオーディションすると、やはり英語のほうが多く喋るという子どももいたりして、なかなか中国語だけで脚本を読ませるというか、台詞が成立しなかったので、その辺はこっちが逆に順応しないといけなかったです。エシュリーに関してはオーディションで、彼女が日本語が堪能だということが分かったというのと、そもそも彼女が言語学専攻だったので、それを生かそうということになりました。
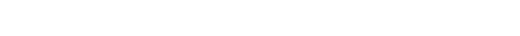


















 Check
Check





