
左から、ナディア・テュランセヴさん、クリスチャン・ヒメネス監督、ジュリー・ガイエさん
10月25日(土)、ワールド・フォーカス『ヴォイス・オーヴァー』の上映後、クリスチャン・ヒメネス監督、ジュリー・ガイエ プロデューサー、ナディア・テュランセヴ プロデューサーが登壇しQ&Aが行われました。
⇒作品詳細
Q:ようこそ、東京に3回目に戻ってきてくださってありがとうございます。
クリスチャン・ヒメネス監督(以下、監督):はい。これが私の3回目の東京です。そして、毎回東京に戻ってくることはとても嬉しい、感動してしまう出来事です。なぜかというと、毎回私の新作を東京の方にお見せできることはとても嬉しいことです。それと同時に、私にとって東京国際映画祭はとても思い出深いところなんです。なぜかというと、この映画祭を通して初めてプロデューサーのガイエさんにお会いして、それ以来ずっと一緒に仕事するようになったからです。
Q:少し補足しますと、2009年に『見まちがう人たち』を出品されて、その時にジュリーさんは『エイト・タイムズ・アップ』という作品で主演女優賞を受賞なさって、その時の縁で次の作品を共同制作されたという経緯があります。
ジュリー・ガイエ(プロデューサー):矢田部さんのおかげです。私にとって東京国際映画祭に戻ってくるということはとても重要なことなんですね。なぜならば、考えてみますと、2009年の事でした。矢田部さんが本当に素晴らしい作品を選択なさって、上映してくださっている。その中で、私たちは素晴らしい人たちに会う機会に恵まれました。その中には、メキシコの監督カルロス・レイガダスさんもいましたし、クリスチャンとも出会い一緒に仕事をするようになったから、私にとっても思い入れのある映画祭です。
ナディア・テュランセヴ(プロデューサー):2009年から全然映画を撮ってなかったということではないんですよ。2011年には『Bonsai~盆栽』という映画で同じく東京国際映画祭にヒメネス監督は出品なさっていますし、私自身はその5年後に久しぶりに日本に来ているわけですけれども、ヒメネス監督とは2作目になるわけです。

Q:ありがとうございます。それでは、さっそく映画についてお話をお伺いしたいとおもいますが、『ヴォイス・オーヴァー』はバルディビアという監督の故郷で撮られた作品だと思います。共同で脚本を書かれているとおもいますけれども、故郷で家族の作品を描こうと思われたきっかけはなんですか。
監督:あえてバルディビアでなくても良いとこの物語については思っているんですね。ですけども、なぜバルディビアにしたかというと、それは小さな都市であるということ。小さな町であるということはこの物語の性質上重要だと思いました。バルディビアというのは実は大学がある町なんです。ということは田舎の小さな都市でありながら、大学がある中で、知的対象がいたり、世界とつながっているということが、物語上とても重要ですし、ぴったりだと思いました。バルディビアの近くにまた小さな町があるんですけれども、そこはやはり大学もないですし、この物語にマッチしないと思いました。重要なのは、この物語というのは、世界中どこでも起こりうる物語だと思います。なので、あえてバルディビアである必要はないんですけれども、とても普遍的なテーマだと僕は考えています。
Q:監督の前作『Bonsai~盆栽』をここで観たときに非常に感銘を受けまして、今回はこのためだけに絶対こようと思ってきました。質問ですが、映画を見ていくうちに子供の視点で、一つ一つ学んで成長していく過程というのをすごく感じました。そういった部分のお話をお伺いしたいと思います。
監督:まず初めに、褒めてくださってありがとうございます。『Bonsai~盆栽』をみた後に、今回また『ヴォイス・オーヴァー』を観に来てくださって本当にありがとうございます。あなたの解釈、私は好きです。映画というのはいろんな解釈があっていいと思うんですね。ですので、僕なりの解釈を付け加えさせていただきます。それは何かといいますと、ソフィアとアナの姉妹がいます。30代ですけれども、この映画では見方によっては子供に返ってしまっているんですね。彼女たちの母親もそうだと思います。おばあちゃんがいて、自分の母親の前ではお母さんも娘になってしまうというわけですね。なので、そういう風に考えると、家族というのは自分の立場で親になったり子供になったり、いろいろ変わっていると思いました。それは僕自身の体験から思っていることなんですけれども、いくら大人になっても子供になる瞬間、または相手があると思います。僕には2人の姉がいるんですが、彼女たちの前にいると、僕はいい大人なんですけれども、子供に戻ってしまうということがありますし、どんな人間でもそういう相手がいると思います。
Q:女兄弟が2人いるとおっしゃっていましたが、この映画に出てくる姉妹に監督の女兄弟を反映させているようなことはあるんでしょうか。
監督:たぶん。やはり人間何か作っているものがあるとしたら、その中には自分のパーソナルな要素が含まれることはあると思います。映画の中でも必ずそうだと思います。それはファンタジー映画であっても作り手のパーソナルな部分が入ると僕は思うんですね。もちろん僕の経験というのはこの映画の中に入っていますし、それと同時に他の人から聞いた話だったり、自分がリサーチした情報も入っています。釘を踏むシーンがあるんですけれども、あれは実は僕に起きたところです。僕が釘を踏んで、妹に全然痛くないよと言ったところ、そのあとに妹も釘を同じように踏んでしまいました。
Q:オープニングシーンがかなりショッキングでありました。あのオープニングシーンに込めた思いを教えて下さい。
監督:ここで皆さんにはっきり申し上げたいのは、あれは決して直接映したものではないです。あれはあくまでも、アントワーンのお母さんが撮ったビデオをコンピューターに入れて、スクリーンを家族が見ている。スクリーンの映像を映しているという設定です。そこにはアントワーンのお母さんのビデオカメラ、コンピューターといくつも間にあってそれで、家族が見ているというのがとても重要なんです。僕は決してお産のシーンを見ていただこうとは思っていませんでした。それであるなら、僕がカメラを据えて撮っていましたから。それではなく、あくまでもアントワーンのお母さんのビデオを撮っている視点であるということ、それを観ている家族の視点であるということをご承知おきください。それがとても重要な意味であって、僕のカメラが撮ったら何の意味もないと思っていました。それから正直言って、僕の映画の解釈を僕から話すということは好きではないんですね。それはひとつに、僕自身の解釈もどんどん変化していってしまうということもあります。映画というのは大きな相対的なものであると考えています。一つ一つの部分をとって、いろいろ説明するとか、映画というものは自分のメッセージを伝える、伝達するチャンネルではないと僕は考えています。その中で、強いてエンディングについて話をすると、正直言ってエンディングは、あのようなエンディングにしようと最初から思っていました。何を象徴しているかというと、新しいもののスタートということと、この映画の中では食べ物がとても重要な意味合いを持っていますので、あの行動で新しいことがスタートするという意味合いを持たせております。ただ、それ以上の説明とか解釈をあえて僕は申し上げたくないです。なぜなら、皆さん方がどのようにご覧になってもいいと思っているんですね。ですから、皆さんがご自由に見ていただいて、感じ取っていただきたいと思います。
Q:この映画のアイディアや始まりを教えてください。
監督:正直言って、僕は神による映画をつくりたいと思いました。そして、『ヴォイス・オーヴァー』というタイトルはずいぶん初期の段階から考えていたんです。先ほども申しましたが、『見まちがう人たち』というのは、どちらかと言うと、視点・視野を描いております。そして今回は、音・台詞というものから物語を考えて映画を作りたいと思いました。その会話、それも家族内での会話に焦点を当てたいと思ったんですね。それと同時に食べ物も重要だと考えました。なぜならば、語られない多くの事が食べ物を通して象徴されている、表現されていると思います。そういうことで、食べ物も重要視して描いたつもりなんですけれども。そもそも映画を作る時、僕はかなりリサーチをします。そして先程も言ったように、自分自身の実体験を織り込むこともあるんですけれども、僕がこういう家族の映画を作っているよ、ということのうわさが広まると、まわりの人間が自分たちの実体験とか、こういう本を読んだらいいよとか、いろいろ教えてくださるんですね。そういうことを全部引き出しにいれて、その引き出しがいっぱい出来上がった段階で、いろんなものをそこの引き出しから取り出してそして一本の映画をつくるということが僕のメソッドです。
台詞がオフという話なんですけれども、脚本の段階から入れておりました。それは、本当に映画の中心的テーマの一つだと考えていたんです。それはなぜかというと、フレームの外で語られているということですね。フレームを皆さん一つの枠と考えてください。そうすると、その見えない人たちがしゃべっているということ、つまり物語の現実、または我々が見えているものの枠の外で語られていること、というようにもなります。それと、もしかしたら、自分たちが話している枠の外のことが語られているかもしれないということで、そのフレームの外・枠の外で語られているということは非常に重要なんですね。なぜ自分がそういったアイディアを思いついたかというと、実はナチスの強制収容所の人たちの記事を読みまして、とても面白いことが書かれていました。実際に、強制収容所にいて、その体験をした人たちよりも、その人たちの子供の世代、強制収容所を経験していない世代の方がよりストレスを感じている。よりトラウマを抱えているという現実があったんですね。それはなぜかというと、苦しみやトラウマが親から子へトランスミットされているというような過程で記事が書かれていました。実際はその逆で、親が自由に体験を話している場合は子供なそんなにストレスを抱えていない。ですけども、親がそのトラウマをあえて語らず、うちに秘めていた家庭の方が、子供はその話を聞いていないにも関わらずそのトラウマが余計に強かった。ということは何かというと、コミュニケーションはとても複雑で面白いものであって、その語られないことがどうにかして受け継がれて、または感じとって、語られていないからこそ、より強く感じることがあるのだな、ということに気が付いて、こういった設定にしました。
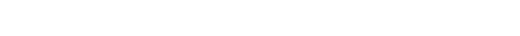


















 Check
Check





