
「制約があるほどコントロールが外れて、結果的にすごいエネルギーを発散する。まさにこの映画がそれでした」――ケヴィン(監督/脚本/プロデューサー/作曲/音楽)、クリストファー・ドイル(撮影監督)
作品詳細
デジタル時代の旗手と称されるフィリピンのケヴィン監督と、世界的な撮影監督として評価の高いクリストファー・ドイル、そして国際的な活躍が著しい浅野忠信が加わった『壊れた心』。カオスの街マニラを舞台に、詩人でミュージシャンでもある監督のマルチな才能を投入した作風は、パンクオペラのような味わい。そのパワフルで、猥雑で、しかも詩情豊かな“恋の逃避行”を撮り上げたケヴィン監督とクリストファー・ドイルにお話を聞きました。
――このエネルギッシュな愛の逃避行を撮ろうとしたきっかけは何ですか?
ケヴィン監督(以下、ケヴィン):3年ほど前に愛の詩を書いて、それを元に撮った短編映画がベルリン映画祭で上映されました。そこからどんどん雪だるま式に話が膨らんでいき、プロデューサーのステファン・ホールが関わって、彼の知り合いだったクリス(クリストファー・ドイル)などが加わって、みんなを合わせたらどうなるんだろうか? X+Y+αはどうなるんだろう、と思ったらこんな風に爆発してしまいました(笑)。
――撮影する前に、監督からはどんな風に撮って欲しいと言われましたか?
クリストファー・ドイル(以下、クリス):だいたい時間もかけられないし、カメラの台数も限りがあって選択肢がない状態で突っ走るしかなかった。実は浅野さん(主人公の殺し屋役)の身体にカメラを括り付けて撮ったりもして、いってみれば半分ぐらいは彼が撮ったようなもの。撮影監督は私じゃなくて浅野だよ(笑)。
ケヴィン:エネルギーというのは、けっして好条件だから生まれるというものでもない。最終的には“人”なのだと思います。いろんな人の力のコラージュとでもいいますか。限られた条件のなかで自分でも思ってもいない方向にプッシュされて、制約があればあるほどコントロールが外れて結果的にすごいエネルギーを発散する。まさにこの映画がそれでした。
クリス:それとともに、やっぱり街だろうね。いろんな要素がミックスされている。交通渋滞に巻き込まれる、ものすごい雨に降られる、そういう環境に反応するというのかな。その環境でカメラを回し、臨機応変に映像を切り取っていくことが大事なんだと思うよ。

――浅野忠信さんとコラボをした感じはいかがでした?
ケヴィン:これまで8〜9本ほどご一緒していますが、いつも素晴らしい体験です。彼はボタンを押すだけで役に入れるような俳優。ある日はヒットマンかと思えば、次の瞬間は繊細な男になれる。黒沢清作品に出演しているときから大好きでした。
クリス:いっしょに仕事をした俳優のなかでもトニー・レオンと浅野は別格。何もしなくていい。「ただ見ていたい!」と思わせる俳優だよ。シンプルで何もしないのにすべてが備わっているんだ。
――これまでウォン・カーウァイなど多くの巨匠とコラボしてきましたが、ケヴィン監督との仕事は刺激的でしたか?
クリス:どの監督も同じことが言えるのだが、いつも彼らが持っているエネルギーに刺激されます。セックスと同じですね。僕はベッドではダメなので、刺激は映画を撮ることで見つけるしかないんだ(笑)。
――ケヴィン監督とはエクスタシーを感じましたか?
クリス:何度も、何度も(爆笑!)
――台詞は少なめですが、バックに流れる曲が出演者の心情とシンクロして雄弁に物語を語っています。ミュージシャンでもある監督ならではの演出だと思いますが。
ケヴィン:音楽に関しては、もちろん事前に準備をしていることもたくさんあるのですが、結局それ以外のアクシデントが起きてしまい、そのチャンスに乗った、というところもありました。例えば最後に流れる音楽は、事前に作曲はしてあったのですがレコーディングしたのは撮影が終わる直前。それまでに撮ってきた映像、物語に似合う詩を作って録音しました。
――本作品はコンペティション部門への参加ですが、映画祭を楽しんでいただければうれしいです。
ケヴィン:もちろん、楽しんでいます。この作品は2〜3年間も大事に暖めて育ててきた赤ちゃんみたいなもの。去年、撮影が終わって、ポストプロダクションもドロドロになるほど大変でした(笑)。なので、やっと皆さんに見ていただける、この東京国際映画祭での上映が映画にとってのお誕生日みたいな感じです。後は成り行き任せ。評価や反応は、コントロールできませんからね。
取材/構成:金子裕子(日本映画ペンクラブ)
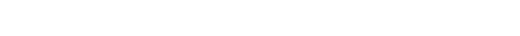


















 Check
Check





