
10/26(日)、コンペティション『神様なんかくそくらえ』の上映後、ジョシュア・サフディ監督、ベニー・サフディ監督、アリエル・ホームズさん、ケイレブ・ランドリー・ジョーンズさんをお迎えし、Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
ジョシュア・サフディ監督(以下、ジョシュア監督):(日本語で)「ありがとうございます。私の弟はベンジャミンです。」

ベニー・サフディ監督(以下、ベニー監督):(日本語で)「よろしく。」日本でこの映画を皆様に紹介できて、非常に光栄に思っています。

ジョシュア監督:一番最初にこの東京国際映画祭で僕たちの映画が上映されるって聞いたときに、ちょっと思ったのですけれど、どういうわけか日本の人の夢とこの映画は交差するところがあったのかな、と思いました。そして、ここにアリエル・ホームズとケイレブ・ランドリー・ジョーンズという主演の二人も一緒に連れて来られて非常に嬉しいと思っています。
Q:ありがとうございます。アリエルさん、一言ご挨拶いただけますか。
アリエル・ホームズさん(以下、アリエルさん):この映画はものすごく素晴らしいと思っています。色々な意味で、色々なレベルで成功したと言えると思っています。これは私の人生についてのお話です。

Q:ありがとうございます。ケイレブさん、先ほど控室で、僕には振らないでくれとおっしゃっていましたが、どこまで本気かわかりませんが。ケイレブさん?
ケイレブ・ランドリー・ジョーンズさん(以下、ケイレブさん):日本に来れて非常にうれしいです。これ、マジで、言ってるんですけど。ここで見せられるなんてほんとに嬉しいし、みんな来てくれて本当にありがとう。これ以上、言うことないよ。

Q:ありがとうございます。アリエルさんが、「これは私の物語です」とおっしゃいましたが、まず私からベニーさんとジョシュさんに聞きしたいんですけど、どうやって彼女と出会われて、どうやって彼女の物語を映画にすることになったか、その経緯を教えていただけますか。
ジョシュア監督:実は他の映画でリサーチをしてまして、ニューヨークの47丁目、ダイヤモンド地区と呼ばれているところでリサーチしていました。コスチュームに身を固め、偽のロレックスを売るという形でリサーチをしていました。その日のリサーチが終わって、地下鉄に乗ろうとしたときにアリエルを見たんです。その時私は、映画のプロデューサーに言ったんですけれども、「なんてきれいな子なんだろう、なんて美しい子なんだろう」。この映画(そのときリサーチしていた映画)に出てもらおうじゃないか、ということで、話しかけたんです。その時彼女はとても素敵な恰好、きれいな格好をしていて、ダイヤモンド地区で働いているというふうに言っていました。そして「映画を作っているんだけれども、出てくれないか」と話をしたら、「あ、いいわよ」ってちょっと疑い深そうな感じで言ったんです。そして、1週間後に会いまして。そのときは全く違う格好をしていました。彼女は年中住所が変わりまして、ディナーの途中で「実は私、ホームレスなの」という話をしました。そして、この映画に出てくるキャラクターなんですけれども、「イリヤがどうだ」「イリヤがああだ」と、イリヤという人についてたくさん話をしていました。その話をしていて、非常に感動したんですね。「もっとこの人のことを知りたい」「彼女をことを知りたい」と思いました。アリエルのことを知れば知るほど、もう一つの映画に興味が無くなっていったんですね。そして、彼女ともっと親しくなって、リチャード・カーンのミュージックビデオに彼女を出られるようにしてあげたのですが、彼女はその時、現れませんでした。どうしたのだろうと思っていたら、数週間後に彼女から電話があって、「実は病院にいた。自殺しようとしたんだ」と言いました。そのとき、ロサンゼルスに住んでいた友人と話をしていたんですけれども、「彼女の話を映画にしたほうがいいんじゃないか」と言いました。
ベニー監督:僕はジョシュからアリエルの話を聞いたんですけれども、彼女に自分の話を、自分の人生を書いてくれ、と頼みました。そして、紙に書かれたものを読んだんですけれども、これは、こういうタイプの物事についてとてもスペシャルな、特別な見方をしているなって思いました。そして、これを映画にしたいと思いました。
ジョシュア監督:宇宙的な意味で、こういう流れには従っていくしかなかったんだよね。
ベニー監督:結局彼女はその物語を書いて、それを僕たちが脚色するという形になりました。そういった力が働いているんで、もう無視することはできないんですね。この本自体もものすごい力があって。ディテールとか、いろんな人の名前とか、細かいところまで無視できないほど力強いものがありました。というのが、この短いバージョンの物語の本題です。
Q:そして、もう一つどうしてもお伺いしなくてはならないのが、本人に演じてもらうというのはまた違うチャレンジだと思うんですけれども、それは自然な選択だったんでしょうか。
ベニー監督:ほかの可能性はなかったんです。
ジョシュア監督:彼女がスターだったんです。彼女に会って、映画を作りたいと思ったので、彼女がいなければ始まらなかった。映画っていうのは、ムービースターが必要ですよね。だから、彼女をキャストしなければいけなかったんです。ある意味で、彼女は世界が知らないスターだったと思います。
Q:アリエルさんは、自分が演じることについてすぐに「イエス」だったんでしょうか。
アリエルさん:そうですね。ジョシュと私が会って、自分の物語を書き始めたり、彼と会って話をしたりしているうちに、彼とすごく近くなっていったんです。それから、すごく親しみを感じていき、自分の人生の真実について語り始めました。その話をし始めてから、本当にジョシュがこのプロジェクトに心から興味を持っているっていうのが分かりました。そうすると、ほかの選択肢や話し合いはなく、私がやるという事がすごく自然なことに思えました。実際に撮影を始めたら、思っていたよりももっと自然にできました。
ベニー監督:それに付け加えますと、自分自身を演じるって本当に難しいことだと思います。自分のあまり見せたくない面を見せることをよしとしなければいけないという意味で、すごく自分にとって大変なことを強いるわけですが、彼女はすごくうまくやってのけたと思います。
ケイレブさん:監督もそういうふうにさせなきゃいけないわけだし、我々みんなすごく奇妙なところにいるわけだよね。
Q:主人公の彼女があそこに戻ってくるのが、何なのかということを教えてください。
ジョシュア監督:彼女の本の中で、特に目立ったのは何度も何度も繰り返すということがどれだけ嫌かということです。それが依存症の皮肉なところなのですが、どうしてもやはり繰り返してしまうことなんですね。実は、最初は違うエンディングを用意していたのですが、結局やめました。編集の段階でやめたんですけれども、全部編集し終わった後に、ラフカットの段階で今のエンディングに決めました。つまり、先ほど申し上げたことを強調するためです。彼女は繰り返すということと、その皮肉を強調するために、このようなエンディングにしました。ドラッグには二つの面があって、一つは真実であり、一つはロマンス。それに中毒しているということだと思います。
Q:演技プランで、これはとてもきちっとしたセリフを書き込んだ台本があるのではなく、ジャズのように即興でやった部分がかなりあったのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。
ケイレブさん:監督は僕に、こういうふうにやりなさい、というようなことを言ったのですが、違うなと思うこともありました。そのシーンで、僕の場所はそうじゃないように思ったこともあったんですけれども。でもいい質問、ありがとうございます。
ちょっとタップダンスしたいなっていう気分なんですけれども、それはちょっとだめかな。
ベニー監督:アリエルの本に基づいて、ジョシュと脚本をきっちり描いていきました。そして、脚本、あったんですけれども、実際の言葉遣いについては、役者の方に自由にしてもらった部分もあるんですけれども。ですから、結局は撮影のときに現場で脚本はできていったような感じに結果的にはなりましたが、実際ストーリーとか演出はきっちりつくられていましたし、何度もテイクを撮りました。
ケイレブさん:確かに、最初と終わりがどうなるかということもあったんですけれども、それをどう生かしていくかっていうのは、自分たち役者の責任というか、任されていました。彼女はこの時、どんな感じがしていたとか、僕は彼女にこのときどんな感じにさせなければいけないとか、そういうことをやらせてくれました。映画とは、だいたいカットしてつなげていくものですけれども、この映画というのは非常に実験的に作ったと思うので、そういう意味では、この映画に参加できてとても誇りに思っています。とてもデリケートにつくられていると思いますし、監督さんたちは自分が欲しいものを非常によく分かっていて、それをやるために必要な人たちを雇っていて、自分が欲しいものを作り上げたと思います。すごく美しいストーリーを語っていて、ほかの人には語れなかったストーリーだと思います。また、監督さんは「そんなに大きな演技をしなくていいよ」と言って、演出してくれました。
Q:先ほど、サフディ監督が「彼女の脚本の前では僕たちはどうしようもなかった」とおっしゃられたと思いますが、まさにその通りで、次に何が起こるかわからないような、登場人物たちのフィーリングでつづられていくストーリーだったと思います。ダークな世界観を作っている要因が音楽だと思うんですね。ノンビートでエクスペリメンタルで実験的な音楽が多用されていたと思いますが、この音楽というのは、監督自身の好きな音楽なのか、意図的にこういうダークな世界にしたいから、あえて使ったのかをお聞きしたいです。
ジョシュア監督:両方かもしれません。自分のテイストというか、自分の趣味を前面に押し出すために、音楽を使う映画作家というのは僕はあまり好きではありません。音楽というのは、映画の中から出てくるべきだと思っています。この音楽は富田勲の音楽ですが、僕にとってはとてもロマンチックな音楽だと思いますし、電子音楽、エレクトリックな音楽なので、僕たちはエイリアンバージョンと呼んでいます。例えば、ドビュッシーの曲とかが、とてもエイリアン的にできていると思います。
この映画は私にとってはとてもロマンチックな映画なので、ロマンチックな音楽がいいと思ったのですが、人によってはロマンチックに思わない人もいると思います。富田勲の音楽がとても気に障る、神経に触るっていう人はいるけれども、僕は全然そうではないと思います。ケイレブは慣れろと言いましたけれども、音楽というのは映画の上に乗せるものではなく、映画の中から引き出されているものだと思っています。ジョージ・バーナード・ショーの「音楽というのは地獄へ行くものへの捧げものである」というような言葉があります。音楽というのは魂の言葉であるというか、常に底流に流れているものだと思っています。それで、今回初めて音楽をもの凄く使いました。それと同時に、音楽がない部分もものすごくあるので、ある部分とない部分の対比がものすごくあると思います。
Q:数年前にニュースで観た、ニューヨークでホームレスの人たちが苦しんでいるということが思い出されました。そういうことも踏まえたうえで、こういう生活している人たちがいるということを知った上で、改めて家があることが幸せなのかということ。監督、4人それぞれに、今一番幸せに感じるものは何か知りたいです。愛とか、仕事とか、一番のものが知りたいです。
ジョシュア監督:僕にとっては愛ですね。愛だけが僕を幸せにします。いろんな形の愛があると思いますけれども、もちろん。
ベニー監督:そうですね、そういういろんなものを含んだ意味での愛で。マルチフルな意味での愛ですね。
アリエルさん:私にとっては、あまり混乱していないところで、満足を感じることですね。映画に出ているような、ああいう生活をしている人っていうのは、多くの場合ドラッグ中毒の人が多くて、そのもとにあるのがうつ病だったりするんですね。今、私はドラッグから足を洗って、正気になって、自分を見つめ、現実をしっかり見る視点を得た上で思うのが、その時の私が何を欲していたのか、私がその時何を感じていたのか、ということを考えますと、今は、今の自分に満足を感じることが一番の幸せです。
ベニー監督:もうひとつ付け加えたいのは、幸せを感じるのはその反対のものすごく極端な悲しみのようなものを知らないといけないと思うのです。両極を知ってはじめて幸せが分かるんだと思います。
そして最後に申し上げたいのは、こういう人たちとたくさん知り合って面白いなと思ったのは、「自由」ということです。すごく自由そうに見えます。かなり若い人が多くて、もしやりたければ他の生活も出来たんじゃないかと思えるのです。だから、70代でもう全然体が効かない、ということではなくて、若い人たちなんですね。なので、ホームレスであるということは、選択、決意なんじゃないかと思いました。つまり、いわゆる社会的な契約をするということをしないという決断をするということなんじゃないかなと思いました。でも、面白いのが、人間の無意識には何かあるのかもしれないのですが、制約とか厳格さに引かれる部分というのがあるのではないかなと思うのです。つまり、ドラッグをやっていくことで凄く自由なのに、その中に不自由さというか、厳格さというか、その中に取り込まれてしまうということが起こるので、そういう意味ですごく興味深いと思いました。これは、ライフスタイルの選択だと思いました。
アリエルさん:私はちょっと違う見方をします。最初はもしかしたら選択だったかもしれません。最初は冒険心でやってみたいとか、不幸な状況でそういうことになったのかも知れません。けれども、そこから抜け出せないというのは、チョイスではなくて、彼らが精神的にこの社会で生きていくのに適していないということがあると思います。なので、もしかしたら現実に向き合えない精神的な状態というのもあるのかもしれないし、この世で現実を見つめるのが辛い、ということもあるかもしれないと思います。怠けているとか、働きたくないということではないと思うのです。簡単に選択とも言い切れないと思います。
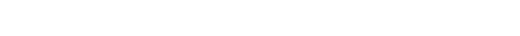


















 Check
Check





