連載企画【東京国際映画祭の重鎮が語る、リアルな映画祭史】を終えて
〜事務局退任のご挨拶~
森岡道夫

皆さま、長い間連載を読んでくださり、ありがとうございました。
実は、取材スタッフから第26回東京国際映画祭の話もぜひ聞きたいと言われました。本来であれば、お話すべきなのかもしれませんが、ちょうど四半世紀と区切りがいいことから、各部門の回顧は第25回までとし、第26回は全体的なお話に留めることにしました。
始まったばかりの新たな四半世紀については、現在のスタッフがゆくゆく丁寧な記録を残してくれると信じております。
さて、私事となりますが、昨年(2013年)末で東京国際映画祭事務局を退任いたしました。この場を借りてお世話になった皆さま、連載を読んでくれた方々にご報告させていただきます。退任のご挨拶を兼ねて、インタビュー連載を終えた現在の心境をお話ししたいと思います。
リュミエールがシネマトグラフを発明し、スクリーンで映像を見られるようになったのは1895年。日本に技術が伝わったのは1897年。そこから数えると、2014年は映画年119歳。日本に伝わってから117年目に当たります。120歳を迎えることを「大還暦」と言いますが、映画はまもなく、ギネスブックの長寿記録に並ぶ年齢になろうとしています。
よく「歌は世につれ、世は歌につれ」と言いますが、映画もまた時代を映す鏡であり、長い時代の変遷の中で成長してきました。無声映画の時代からトーキーになり、白黒がカラーになって、大型スクリーン、3Dとめざましい進歩を遂げてきました。
それと共に、映画の内容も時代を生きた人々の心模様を映しながら、今に至ってきました。第二次世界大戦が終わった当時は、世界中が戦火にまみれていて、その反映であるかのように、イタリアでロッセリーニたちのネオ・リアリズモ運動が起こり、フランスで戦争の悲劇を描いた『禁じられた遊び』が生まれました。
明るい映画の多いアメリカも例外ではありません。『我等の生涯の最高の年』では、大戦で両腕をなくした人物が主人公のひとりを演じています。そんなふうに世界中で戦争の悲惨さが映画になった時代もありました。時代を映す鏡として、文明ともども映画は発展してきたのです。
ここで映画祭の歴史をひも解けば、映画祭御三家のひとつ、カンヌ国際映画祭は1946年にスタートしました。また同年、ベネチア国際映画祭が1942年以来となる復活を遂げています。戦後の貧しい財政事情から、カンヌは中止に追い込まれた年もありましたが、ほぼ毎年開催を続けてきました。先頃、カンヌは第67回、1951年発足のベルリン国際映画祭は第64回の大会を無事終了しました。最古参のベネチアは、この夏、戦前から数えて第71回目を迎えます。
もうお気づきでしょうが、これら三大フェスティバルが映画に出会ったのは、実は映画が青春時代を終えてからのことでした。ベネチアが最も若く映画年37歳、カンヌが51歳、ベルリンが56歳の時です。カンヌもベルリンも、映画が中年真っ盛りの頃に誕生しました。
東京国際映画祭はその数えで言えば、映画が90歳の時に生まれた子どもです。1985年の発足から数えて今年ちょうど30年になりますが、隔年開催の時期があったため、御三家からすれば、まだほんの青二才です。四半世紀と聞くと大事業をやり遂げた気持ちになりますが、本当の実績を出すのはむしろこれからで、先を見据えて努力する必要があるでしょう。
振り返れば、この25年の間に時代は本当に変わったなあと思います。
私が映画祭に関わり始めたのは、ようやくFAXが普及し始めた頃でした。途上国にFAXを入れたら、本当に着いたのか、確認の電話をしなければならなかった。カンヌに通い始めた頃もそうです。受賞結果の一覧をホテルからファックスするから、明朝、ご確認願いますと連絡していたのです。今はカンヌでもベネチアでも、リアルタイムで受賞結果が届きます。IT技術の発達は、世界を一気に縮めてしまいました。
映画界最大の変化は、やはりフィルムがなくなったことです。古代から人類の夢であった「動く写真」は、ジョージ・イーストマンがロールフィルムを作ってくれたおかげで可能になった。ところが今はそのフィルムがなくなり、デジタルへと移行しました。
東京国際映画祭で作品選定の仕事を始めた頃は、市ヶ谷の試写室(日本シネアーツ社)に通いつめ、フィルムを観ることが日課でした。それがのちにヴィデオテープ、DVDと段々コンパクトになり、機材があればどこでも観られるように進化した。さらにいまでは、動画配信でも作品が届く世の中になりました。世間一般の流れをなぞるように、映画祭の仕事もやり方が大きく変わっていった。隔世の感を禁じえません。
事務局員も当初は5〜6名しかいませんでした。事務局長、経理、海外渉外の担当者しかいなかったのが、次第に人数が増えていき、やがて全ての業務を賄える大所帯になりました。それまで各映画会社に増援をお願いして、映画祭を運営していたのです。時代の推移の中で、東京国際映画祭は大きく成長を遂げてきました。
映画祭に在籍していた時の思い出は尽きません。ホウ・シャオシェン監督が審査委員長の「指名代打」を快く引き受けてくれたこと、徳間康快氏に中国問題で助けられたことは、今も深く感謝しています。
作品選定担当者としては、受賞作が大きく羽ばたいていく姿を見るのはうれしいことでした。最もうれしかったのは、グランプリを受賞した作品が2年連続で翌年のアカデミー外国語映画賞にノミネートされたことです。『コーリャ 愛のプラハ』と『ビヨンド・サイレンス』です。このうち、『コーリャ 愛のプラハ』は見事受賞を果たしました。仕事のやりがいを大いに感じた瞬間です。選出した作品が一人歩きして、世間の評価を獲得していくのは、仕事冥利に尽きる思いでした。
また、若い監督が成長する姿を間近に見られたこともうれしいことでした。作品を出品してくれた監督が、後に審査委員を務めてくれるまでになり、再会できるのはまたとない喜びです。折に触れ、監督たちの近況を耳にするだけで、ああ頑張っているなと心温まる気持ちでした。
あえて辛かったことを言えば、年間で何百本という選考作を観ながら、そのほとんどを落とさなければいけなかったことです。選べる本数はコンペの場合、だいたい15本です。苦労して選出したあとは、山のような数のお詫び状を書いてお送りしなければなりません。これには心が痛みました。
誰でもそうでが、長年同じ仕事を続けていれば、自分なりのスタイルができるはずです。
はじめてカンヌに行った時に驚いたのは、マーケットスクリーニングの場合ですが、会場で最後まで映画を観るのが必ずしも常識ではないことでした。最初は満杯なのに、終了すると10人も残っていない。カンヌではこれもありきたりな光景です。世界中の配給業者が駆けつけますが、彼らは冒頭の10分を観て興味がなければ、そこで見切りをつけてしまうと知ったのです。
しかし私はプロデューサーとして、作り手の気持ちになって映画を観る習慣が着いていたので、たとえ興味が持てなくても、最後まで席を立つまいと決めていました。その結果、商業性や自分の好みを度外視しても、作品本意で映画と向き合えたのはよかったです。テクニックはあるけど主題がおざなりなもの、主題は深いけれど表現が拙いものなど、作品ごとの評価をつける中で幅広い判断力を培えたからです。
考えてみれば、映画会社でプロデューサーをやり、それから映画祭の作品選定者になった人間など少ないのかもしれません。映画評論家の草壁久四郎さんは、数々の国際映画祭の審査委員を歴任された専門家でした。また出向で来てくれた映画会社の方々は、日々の業務の延長で映画祭に携わることができたと思います。しかし私はずっと作り手の側にいて、映画祭や配給興行の世界を何も知らなかったから、大変珍しい存在でした。井の中の蛙で飛び込んだのに、よく長続きしたものだと思います。
今にして思えば、プロデューサーの目で長年映画祭を眺めるうちに、ひとつだけ気づいたことがありました。それは映画祭の仕事は、映画製作の過程に大変よく似ているということです。
年が明けたら企画を考え、春先から脚本を作り、夏頃から撮影に入って仕上げ作業を行ない、秋が深まる頃に公開する———。これがプロデューサー時代に染み付いた基本の製作サイクルです。映画祭もこれとほぼ同じスパンで推移します。春先に作品を公募し、海外でも招致活動を行い、作品が決まったら世界に向けてお披露目する。そうして1年に1本ずつ、新しい映画をつくってきたと言えるのです。その意味では、東宝でプロデューサーになってから、ずっと作品づくりに専念してきた思いがあります。そこに、この仕事の醍醐味を感じていました。
27年間も映画祭で働くことができて、つくづく幸せでした。第2回から第26回までをこの目で見届けることができたので、心残りなく若い人たちに後をお任せしたいと思います。
大スターのグレゴリー・ペックやイブ・モンタン、『赤い靴』の撮影監督ジャック・カーディフに会えたことは一生の思い出です。『タイタニック』のワールド・プレミアという歴史に残るイベントに立ち会えたことも光栄でした。今後は、生涯現役としてフリーの立場に戻ります。
長らく在籍した職場を離れるのは寂しいかぎりです。でも、幼い時分から映画と離れたことがないので、これから先も共に歩み続ける覚悟です。そのうち、どこかで皆さんの映画人生と交錯するかもしれません。その節は森岡も元気でやっているなと、温かく見守ってほしいと思います。
本当にありがとうございました。

←連載第1回へ
←連載第2回へ
←連載第3回へ
←連載第4回へ
←連載第5回へ
←番外編1(連載第6回)へ
←連載第7回へ
←連載第8回へ
←連載第9回へ
←連載第10回へ
←連載第11回へ
←番外編2(連載第12(最終)回)へ
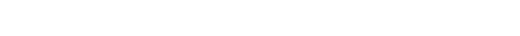


















 Check
Check





