東京国際映画祭事務局 作品チーム・アドバイザー 森岡道夫さんロングインタビュー
第2回 日本国際映画祭から東京国際映画祭へ
──森岡さんは東京国際映画祭の歴史を精力的に調べていて、各年度のレポートをまとめています。
森岡道夫(以下、森岡):歴史を掘り起こしていると面白い出来事が見つかります。なかでも特に思いがけなかったのは、1970年に開かれた「第1回日本国際映画祭」の存在です。これは大阪万国博覧会の一環として開催されたものですが、いまとなっては、憶えている人も少ないのではないでしょうか。
もとを正せば、カンヌ国際映画祭も1937年のパリ万国博覧会がきっかけとなって始まりました。国が威信をかけて科学技術を競い合うなかで、映像文化は脚光を浴びてきます。そうしたなか、万博の催し物のひとつとして、映画祭は発展を遂げてきたのです。
──東京国際映画祭が始まる前に、その前史とも言える映画祭があったのですね。
森岡:これは当時、東映の社長で、映団連会長を務めていた大川博さんが旗振り役となって生まれた映画祭です。1954年から「東南アジア映画祭」(アジア太平洋映画祭の前身)が開催されてきましたが、アジアだけでは意味がない。カンヌやヴェネツィアを見習って国際映画祭をやりたい。大川さんには、そんな強い願いがありました。
そして日本初となる国際映画祭を実現させるために、城戸四郎(松竹)、永田雅一(大映)、松岡辰郎(東宝)、堀久作(日活)、川喜多長政(東宝東和)、森岩雄(東宝)からなる特別委員会が作られました。いずれも日本映画界をリードしてきた錚々たる方々です。こうして映画会社のトップが一丸となって、国や産業界に働きかけて、万博という国家プロジェクトのなかで国際映画祭をやろうとなったのです。
──第1回日本国際映画祭の規模はどんなものだったのでしょう?
森岡:万博第2会場である大阪フェスティバルホールで、1970年4月1日から10日間開催されました。上映本数は20本で、作品選定を登川直樹(映画評論家)、飯島正(映画評論家)、池島信平(ジャーナリスト)、遠藤周作(作家)、荻昌弘(映画評論家)、曽野綾子(作家)、八住利雄(脚本家)の7名が行いました。このときは国際映画製作者連盟(略称:国際映連)との話し合いでコンペ形式ではなく、各国の理解と友好、文化レベルの向上を名目に上映されました。
──ラインナップを見ると、『サテリコン』『野性の少年』『素晴らしき戦争』など、その後一般公開されて高い評価を得た作品が並んでいます。『Z氏』はのちに『Z』として公開され、アカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。
森岡:フェリーニ、トリュフォー、アッテンボローを始め、海外から多くのゲストが参加しました。女優ではジャンヌ・モロー、クラウディア・カルディナーレが来日しています。
私はこの頃、東宝で『父ちゃんのポーが聞こえる』の製作が始まっていたので、会場へ行く余裕はなかったけれど、『私は好奇心の強い女』が修正だらけで上映されて、世間を賑わせたのを憶えています。アメリカではケネディ大統領夫人のジャクリーヌが、「メッセージ性のあるいい映画だから、著作権を侵害すべきではない」と言って無修正で上映されましたが、日本では45箇所も黒味が入ることになりました(笑)。
──第1回日本国際映画祭はいろんな意味で大いに話題を呼んだみたいですね(笑)。第2回以降はどうなったのでしょう?
森岡:国際映連の認可を得てせっかく開催されたというのに、残念なことに翌年大川さんがお亡くなりになり、1回だけで終わってしまいました。それから雌伏15年、1985年のつくば万博のときに、東京国際映画祭が始まるのです。
──ではそろそろ、東京国際映画祭の話題に入りたいと思います。森岡さんが事務局に入ったのは第2回のときですが、第1回(1985)のこともお調べになっていますね。
森岡:東京国際映画祭は日本国際映画祭とは逆で、まず通産省(今の経産省)からの熱心な誘いがあって発足した映画祭です。1985年につくば万博が開かれることになり、その2年前に話を受けて、では、映画界も一致協力しようとなって立ち上がったプロジェクトです。1983年3月に組織委員会が結成されました。会長は財界の大物、瀬島隆三氏で、瀬島さんの肝煎りで運営母体である東京国際映像文化振興会という財団が設立されました。ふつう財団設立には日数がかかりますが、このときは瀬島さんの顔ですぐに認可が下りたということです。
──現在では、秋に映画祭を開催していますが、第1回は5月ですね。
森岡:日本国際映画祭同様、万博が始まって間もない時期(万博は3月開催が原則)の開催を国際映連に申請したところ、「ベルリンが終わってカンヌが始まる大切な時期に、新参者が参入するなどとんでもない」と言われてしまった(笑)。粘って交渉した結果、第2回から秋開催とする約束で、第1回は5月31日から9日間の日程に決まりました。

当時のメイン会場の一つ、NHKホール
──東京国際映画祭ではコンペ形式になります。
森岡:長編映画のコンペ部門を持つ国際映連認可の映画祭は、当時11都市で開かれていました。新参者の東京国際映画祭が歴史あるカンヌやヴェネツィア、ベルリンに太刀打ちできるはずはない。そこで東京の特色を出すために、ヤングシネマ・コンペティションが設立されました。当時の正式名称は「国際新進監督コンクール ヤングシネマ85」です。これは大賞受賞者に次回作の製作資金を賞金として提供しようという、当時も今も大変珍しい性格のコンクールでした。
公募条件は、1945年以降に生まれた監督による16ミリか35ミリの劇映画で、上映時間が60分以上あること、1980年以降に製作された作品であること、該当する監督の最新作、もしくは1本前の作品であること、日本で商業公開されていないこと、国際映連に加盟する他の映画祭で受賞した作品でないこと、過去の商業公開作が5本以内であること、でした。
──「新進監督」という割には年齢層が幅広いですね。5年以内に製作されたもので最新作でなくてもよいなど、作品対象にも幅があります。
森岡:戦後生まれという条件は40歳の中堅どころまで対象になりますが、当時、監督になるには撮影所に入って助監督を経験してと、長いスパンが必要でした。それで年齢層に幅を持たせたのだと思います。作品に幅があるのは、今のように安価で軽量な機材がなくて、そんなに簡単に映画を作れる時代ではなかったからでしょうね。5年以内の作品だったら、新作でも前作でも自信のあるほうでよいという選択肢の持たせ方に、時代性が表れています。
──次回作の製作資金というのは幾らだったのですか?
森岡:総額150万ドル。当時のレートで3億5千万円です。最初は、大賞に選ばれた作品の監督に全額授与する決まりでした。ところが審査委員が議論するなかで、この決まりが変更され、最終的に賞を与えた3人の監督に金額が分け与えられることになりました。
大賞に輝いた『台風クラブ』の相米慎二監督に75万ドル、最優秀監督賞に輝いたハンガリーのペーテル・ゴタール監督に50万ドル、小津安二郎記念賞が授与されたトルコのアリ・オズゲントルク監督に25万ドル。それぞれ次回作の資金として贈られたのです。
──当時は与えられた資金をもとに作品をつくり、第2回映画祭で上映するのが決まりだったのですね。
森岡:当時は隔年開催でしたから、1987年の第2回東京国際映画祭で上映する規約がありました。相米監督とゴタール監督は順調に次回作を撮りあげました。ところがオズゲントルク監督の場合、トルコがこの後もの凄いインフレになり、ドイツのプロデューサーに援助を求めて苦労して作品を作りますが、最後に赤字を背負うことになってしまった。2000年のイスタンブール国際映画祭に審査委員で呼ばれたとき、久々にオズゲントルク監督に会ったら、「今となっては笑い話だが」と言ってそんな話をしてくれました。
デヴィッド・パットナム審査委員長(プロデューサー)のもと、レイモンド・チョウ(プロデューサー)、ベルナルド・ベルトルッチ(監督)、イシュトヴァン・サボー(監督)、今村昌平(監督)といった大家が国際審査委員を務めましたが、次回作の資金を提供したことで監督がツケを払うことになるとは、思ってもみなかったでしょうね(笑)。
──作品選定は誰が担当されたのですか?
森岡:ATGの佐々木史朗さん(現・日本映画大学理事長、オフィスシロウズ代表)が担当しました。レフェレーションを作って作品を公募する傍ら、世界を飛び回って作品を集めてくる。そんな今やっている活動の先鞭をつけたのが佐々木さんです。ジャンル別、国別でバランスを考えながら選んでいき、2年の準備期間のうち1年は、ほとんど日本にいなかったそうです。私は第2回のとき映画祭に入って作品選定をやりましたが、佐々木さんにはだいぶ教わりました。
──ヤングシネマ以外にはどんな部門があったのですか?
森岡:コンペ部門はヤングシネマだけで、その他の自主企画に、「映画祭の映画祭」「日本映画の昨日と今日」がありました。前者はいまで言う「WORLD CINEMA」と「特別招待作品」の合わさったようなもの。後者はのちに展開される「ニッポン・シネマ・クラシック」「NIPPON CINEMA NOW」の走りです。また協賛企画に、「東京国際ファンタスティック映画祭」「カネボウ国際女性映画週間」「テラビナ・アニメフェスティバル」などがありました。
当時は部門ごとに外部スタッフが企画を立てる体制で、ヤングシネマが佐々木さん(ATG)、「映画祭の映画祭」が川喜多和子さん(フランス映画社)と堀江鈴男さん(東急レクリエーション)、「日本映画の昨日と今日」が黒井和男さん(キネマ旬報社)、「東京国際ファンタスティック映画祭」が小松沢陽一さん(映画評論家)、「カネボウ国際女性映画祭」が高野悦子さん(岩波ホール)、「テラビナ・アニメフェスティバル」が今田知憲さん(東映動画)の担当でした。各人が所属会社の社員や信頼できるスタッフを集めて、上映プログラムをつくりました。
──東京で初めて開かれる国際映画祭ということで、だいぶ盛り上がったようですが。
森岡:開催場所となった渋谷で大々的なパレードを行い、オープンカーに乗った映画人が手を振って声援に応えたり、109に映画祭をアピールするチャップリンのシリンダー広告を掲げたり、渋谷駅前広場に和田誠さんによる映画祭モニュメントを設置して除幕式を行ったりと、それは盛大でしたね。またオープニングでは黒澤明監督の『乱』が上映され、仲代達矢(俳優)が上映会場に現れなかった黒澤監督のメッセージを代読したのは有名な話です。
私はちょうどこの時期、プロデュース作の海外ロケに同行していて日本にいなかったのですが、映画祭に入って資料を調べるうちに、あらためて規模の大きさに驚かされました。参加した映画人によるチャリティ・テニス・トーナメントの模様をフジテレビが中継した資料も残っています。

パレードの模様(左)/109シリンダーのチャップリン(右)
──ゲストにはどんな方々がいらしたのですか?
森岡:ハリソン・フォード(俳優)、ソフィー・マルソー(女優)、シェール(女優)、ジャンヌ・モロー(女優)の他に、当時はもうあまり映画に出ていなかった名優ジェームズ・スチュワートが駆けつけてくれました。監督ではヘクトール・バベンコ、パトリス・シェローらが参加しています。日本のゲストも大勢訪れましたが、外国人記者との会見の場が設けられて、黒澤監督がサイン攻めに会う一幕もありました。

記者会見時のハリソン・フォードさん(左)/ジェームズ・スチュワートさん、中曽根康弘総理大臣(当時)、ジャンヌ・モローさんがオープニングイベントに登壇(右)
──続いて、第2回映画祭(1987)に進みたいと思います。お話にも出ましたが、森岡さんはこのとき初めて映画祭入りしました。
森岡:当時、映画祭の本部(母体となる東京国際映像文化振興会)は、銀座並木座の向かいの小さなビルにあって、常駐スタッフは5~6名ほどでした。1986年の秋に話があり、ヤングシネマ部門の選定を社団法人日本映画テレビプロデューサー協会(会長:川口幹夫)が引き受けることに決まり、翌年から私が担当として本部に通い詰めることになります。このときは、第1回は派手にやりすぎて賞金も弾みすぎだという意見が出たため、地に足付いた映画祭にしようという気運が高まっていました。
今の東京国際映画祭の基盤が出来たのは、この第2回だったと考えています。瀬島隆三会長のもと、新たにニッポン放送の石田達郎氏がゼネラルプロデューサーに就任し、「世界の東京」をアピールすべく、観客参加型の映画祭を目指しました。その理念は、いまも映画祭に受け継がれています。
──第1回はヤングシネマ・コンペティションだけでしたが、第2回にインターナショナル・コンペティションが新たに設立されました。いったい、どんな経緯があったのでしょう。
森岡:カンヌやベルリン、ヴェネツィアを目標とするには、ベテラン監督も参加できるコンペ部門を持たないわけにはいきません。それでインターナショナル・コンペ部門を創設することになりました。当時は、ヤングシネマ部門は日本映画テレビプロデューサー協会、アジア映画部門は日本映画製作者連盟、日本映画部門はキネマ旬報社という役割分担がありましたが、このインターナショナル・コンペ部門だけは合議による作品選定制度を採用していました。メンバーは石田ゼネラルプロデューサー、草壁久四郎(映画評論家)、原正人(当時、ヘラルドエース)を始めとする、洋画に精通しておられる9名の方々です。
──森岡さんが作品選定を担当したヤングシネマ部門は、第2回目では規定など、変化がありましたか?
森岡:ヤングシネマについては、前回話したように、プロデューサー協会の中で協力者を募り、各人を担当地域に派遣して作品選定をお願いしました。また、応募基準を改め、35歳未満の監督で、商業公開された作品が5本以内であること(35歳以上でも1本目の作品であれば可)、1985年6月以降に製作された作品であること、16ミリ、もしくは35ミリの劇映画で上映時間60分以上であること、日本で商業公開されていないこと、他の国際映画祭に出品されていない作品であること、としました。
──2つのコンペ部門ができて、審査委員や賞金形態はどんなふうに変化したのですか。
森岡:インターナショナル部門の国際審査委員が、ヤングシネマ部門の審査委員を兼任しました。グレゴリー・ペック審査委員長(俳優)を筆頭に、クロード・ベリ(監督)、アラン・パーカー(監督)、ムリセル・ナン(監督)など海外組が7名、日本からは篠田正浩(監督)、登川直樹の2名です。
賞の顕彰ですが、インターナショナル部門はトロフィと賞状のみで賞金はなし。ヤングシネマ部門は次回作の製作と上映という規約をなくして、通常の賞金制度となり、大賞となるさくらゴールド賞に2千万円、副賞のさくらシルバー賞に1千万円を授けることになりました。前回はドルでしたが、このときから円建てになります。
──グレゴリー・ペックは大変な人格者として知られています。
森岡:「私は俳優をしていますが、みなさんご存知ないでしょう。かつてオードリー・ヘップバーンという有名な女優がいましたが、その一世を風靡した作品で横に立っていた男です」と挨拶して、万雷の拍手を浴びていました。とても好感の持てる人物でした。

グレゴリー・ペックさん(右)と、1960年のアカデミー賞美術賞を『アパートの鍵貸します』で受賞した、美術監督アレクサンドル・トローネルさん(左)
──たくさんの作品を見ることになって、国際審査委員もさぞ大変だったのではありませんか。
森岡:第2回の特殊事情として、ヤングシネマ部門では、まず国内の予備選考委員が4本の作品を選び、それを国際審査委員に見てもらって受賞作を決める方式を採りました。予備選考委員はプロデューサー協会のなかから選んだ人員で構成されましたが、NHKの大河ドラマで今も活躍している方もいます。テレビの作り手も映画への興味は旺盛で、大いに力を注いでくれました。
──このとき、大山勝美さんがフィンランドから、アキ・カウリスマキの作品を持ってきてくれたのですよね?
森岡:カウリスマキの『パラダイスの夕暮れ』は、成瀬巳喜男風のとてもいい作品でした。それから、ジャン=クロード・ローゾンの『夜の動物園(TIFF上映タイトル『ナイト・ズー』)』(カナダ)は原正人さんが推して私もいい作品だと思いましたが、アート系の作風が独特でしたね。ソ連映画『翌日戦争が始まった』は、本国で公開を見送られてきた作品で、新作といっても少しタイムラグがありました。
さくらシルバー賞に輝いた『ホテル・ロレイン』(アメリカ)は、廃館になるホテルを舞台にした「桜の園」風の爽やかな作品。さくらゴールド賞に輝いた『キッチン・トト』(イギリス)は、ケニアを舞台に、白人との友情の板挟みなるアフリカ人の悲劇を描いた物語で、監督は香港出身のハリー・フックです。『祖国アフリカ(TIFF上映タイトル『チョイス』)』を出品したブルキナファソ出身のイドリッサ・ウエドラオゴと『天菩薩』のイム・ホーは東京国際映画祭初参加でしたが、その後の出品作でグランプリを受賞し大きく羽ばたいていきました。
──ゲストは若手からベテランまでバラエティに富んでいたそうですね。
森岡:皇太子殿下と妃殿下(現在の天皇皇后両陛下)がオープニング・セレモニーにご臨席されました。海外ゲストも豪華で、エリア・カザン(監督)、ジューン・アリスン(女優)、アレクサンドル・トローネル(美術監督)が中曽根首相を表敬訪問しています。またブライアン・デ・パルマ(監督)、オリバー・ストーン(監督)、タヴィアーニ兄弟(監督)、イ・チャンホ(監督)が作品上映に併せて来日しました。チャン・イーモウ〔張藝謀〕はこのとき俳優として来日し、主演作『古井戸』がインターナショナル部門でグランプリと主演男優賞の2冠に輝きました。
『普通の女』で主演女優賞を獲得したレイチェル・ウォードは、『カリブの熱い夜』が公開されていて、当時は人気女優のひとりでしたね。日本からは三船敏郎(俳優)、岸恵子(女優)、石坂浩二(俳優)、中井貴一(俳優)、大島渚(監督)らがパーティに参加してくれました。個人的には、外国人プレスを黒澤明監督に会わせるために、バス3台に乗せて箱根プリンスホテルへ行ったことが記憶に残っています。「世界のクロサワ」と記念撮影するプレスのために、にわかカメラマンとして何枚もシャッターを押しました(笑)。
──いまはDVDで応募するケースが多いですが、当時は応募作品を見るにも苦労されたのではありませんか。
森岡:ビデオテープすらまだ普及してない時代だから、みんなで試写室に行ってプリントを見ることになります。運賃も高価で、フィルムを5~6巻海外に送るだけで片道5万円くらいかかります。応募してくるときは先方の負担ですが、返却する際は事務局の負担になるので莫大な費用がかかりました。
──他の上映部門にはどんなものがありましたか?
森岡:自主企画では、「映画祭の映画祭」を変更して「特別招待作品」が新たに設けられ、オープニング作の『竹取物語』、クロージング作の『ラスト・エンペラー』の他、『アンタッチャブル』『グッドモーニング・ヴァビロン』などが上映されました。それと、「アジア太平洋秀作映画祭」がこの年から始まりました。協賛企画では「東京国際ファンタスティック映画祭」「カネボウ国際女性映画週間」の他に、「フェデリコ・フェリーニ映画祭」などが開かれました。当時は部門ごとに劇場を分けていました。インターナショナル部門は渋谷パンテオン、ヤングシネマ部門は渋谷東宝、特別招待作品はNHKホールです。1作品につき1回限りの上映だったこともあり、大きな会場を使っていました。東京国際ファンタスティック映画祭は渋谷東急がメイン会場でしたが、この劇場があった場所はヒカリエになっていますね。

渋谷パンテオン、渋谷東急が入っていた東急文化会館(1985年当時)
──第2回は当初の約束通り、会期は秋に移ったのですよね。
森岡:具体的な時期は国際映連と調整して決定しました。第2回は9月25日から10月4日までの10日間で、この後、第9回(1996)まで9月末開催10月初旬終了が続きます。観客も熱狂的で、映画祭のファンはこの頃から増えてきたと思います。109にマリリン・モンローのシリンダー広告を掲げ、渋谷は映画祭ムード一色でしたが、当時は上映会場が分散していたため、会場間の移動に時間がかかるなど不自由な点はありました。

109シリンダーのマリリン・モンロー

取材 東京国際映画祭事務局宣伝広報制作チーム
インタビュー構成 赤塚成人
今回のお話しの過去TIFF詳細はポスター画像をクリック!
(TIFFヒストリーサイトへリンクします)


←連載第1回へ
連載第3回へ→
連載第4回へ→
連載第5回へ→
番外編1(連載第6回)へ→
連載第7回へ→
連載第8回へ→
連載第9回へ→
連載第10回へ→
連載第11回へ→
番外編2(連載第12(最終)回)へ→
連載終了のご挨拶:森岡道夫→
TIFF 公式サイト TOPページへ
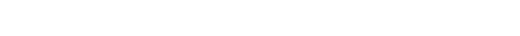


















 Check
Check





